【本日のお悩み】
○色々支援してるけど、成果がでない
○いつまでも子どものやる気が見えない
○どうすれば子どもがやる気を出すのか知りたい
子育てや教育の場で、親御さんや支援者の方が熱心にサポートしているにもかかわらず、「なぜか成果が出ない」「子どもがなかなか成長してくれない」と悩む声をよく聞きます。その背景には、一つの重要な要因が隠れています。
それは、子どもの「やる気」や「将来への見通し」です。
やる気や見通しがないと、支援の効果は薄い
親や支援者がどれだけ時間や労力をかけて環境を整え、サポートを提供しても、子ども自身に「これを成し遂げたい」「自分はこうなりたい」という内側からの意欲や、将来に対する明確な見通しがなければ、その支援効果は残念ながら薄くなってしまいます。
例えば、目の前に豪華なごちそうが並んでいても、お腹が空いていない人には響かないのと同じです。外側からの働きかけは、あくまできっかけやサポートでしかありません。成長のエンジンは、常に子ども自身の心の中にあるのです。
「自分で気づく」瞬間が最大のチャンス
では、成長のエンジンを動かすための鍵は何でしょうか?
それは、子どもが「自分はこれができるようにならなきゃいけない」「このままでは困る」と、自ら気づく瞬間です。
この「気づき」は、単なる知識として教えられるものではなく、実体験や内省を通じて子ども自身が獲得するものです。この「気づき」が得られたときこそ、親や支援者のサポートが最も大きな効果を発揮する最大のチャンスとなります。
「困る環境」が気づきを促す
具体的な例として、「忘れ物をなくす」という課題を考えてみましょう。
親が子どもに忘れ物をなくしてほしいと思っていて、毎日口を酸っぱくして「明日の準備ちゃんとしてね」と声かけをしても、子ども自身が「忘れ物をすると本当に困る」と思っていなければ、その声かけの効果は薄いでしょう。親の指示だからやっている、という受け身の姿勢では、習慣化や内面的な成長にはつながりません。
逆に言えば、子どもが忘れ物をして困る環境をあえて作ってあげることが、子どもが自分で気づく可能性を高めます。
親が完璧に準備を手伝いすぎたり、忘れ物を届けたりすることは、短期的には親切かもしれませんが、長期的には「困る経験」を奪ってしまいかねません。子どもが「困る」状況に直面することで、「もう忘れ物でこんな嫌な思いはしたくない」「忘れ物をしないように自分で対策を立てよう」という内発的な動機が生まれるのです。
さいごに:あえて「困る環境」を作ってみる勇気
もちろん、子どもを危険な目に遭わせたり、過度なストレスを与えたりする必要はありません。
しかし、子どもの成長を願うのであれば、時にはあえて子どもが自分で解決しなければ「困る環境」を作ってみることも、一つの有効な手段かもしれません。
子どもが失敗したり、困ったりするのを見るのは、親や支援者にとっては心苦しいことです。
ですが、その「困った」という経験こそが、子どもに「気づき」を与え、次の成長への一歩を踏み出すための、何物にも代えがたいエネルギー源となるのです。
親や支援者の役割は、「全ての問題を解決してあげること」ではなく、「子どもが自分で気づき、成長していくためのステージを用意すること」なのかもしれません。
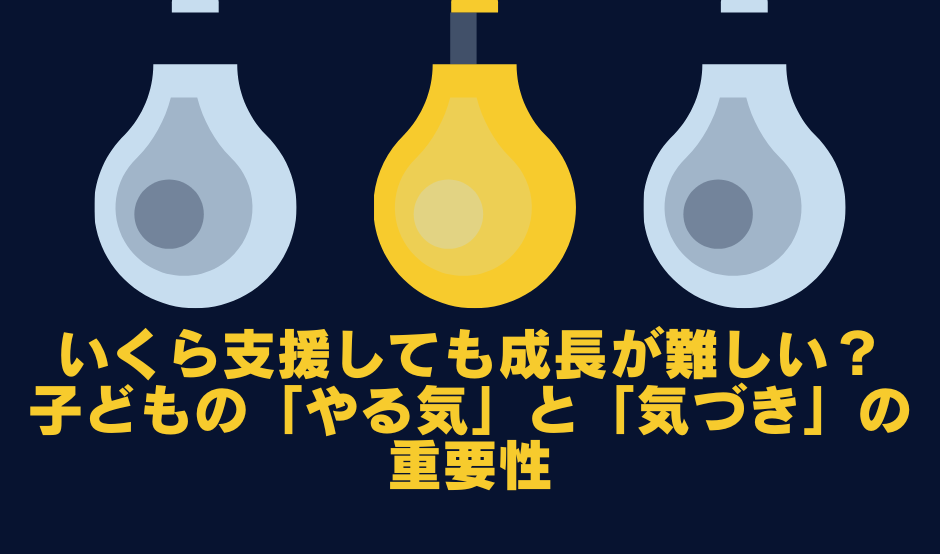
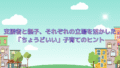
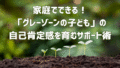
コメント