【本日のお悩み】
○学童保育や放デイに毎日は行かせられない
○仕事でどうしても留守番させないといけない
○短時間だけでも子どもひとりにして大丈夫かな
お悩み解消ヒント:安全面には気をつけながら、子どもの自立を促す期間と考えてみて
夏休みは長期にわたるお休み。とはいえ、保護者が毎日付き添えるとは限りませんよね。
「本当は子どもと過ごしたいけど……」と思いながら仕事に向かう方も多いでしょう。
学童保育や放デイを活用するのはもちろんですが、子どもによっては毎日行くことで疲れてしまったり、「毎日は行きたくない」という気持ちが出てくるかもしれません。利用料金や昼食代といった金銭面の問題も出てきますね。
(実はブログ主も、昔で言うところの「鍵っ子」でした。
当時は学童保育や放デイなどなく、親は共働き。たまに祖母が来てくれていましたが、毎日というわけではなく……一人の寂しさを感じることもありましたが、私は割と早く慣れました。自宅でテレビを見たりお絵かきしたり、プールや図書館に行って自由気ままな一人の夏休みを過ごしていた記憶があります。ただ、これはあくまで私のパターンなので、ご注意を)
具体的な方法:4つのポイントを紹介
まずは「ルーティンづくり」から
子どもが安心して過ごすには、「今日は何をする日か」が明確になっていることが大切です。
例:午前中のルーティン(参考)
8:00 起床・朝ごはん
9:00 学校の宿題やドリル
10:00 読書タイム
10:30 自由時間(お絵描き・パズル・動画など)
12:00 お昼ごはん(用意されたものをチンして食べる)
時計の読める子であれば、簡単なスケジュール表を壁に貼っておくのがおすすめです。
イラスト付きの「やることチェックリスト」も視覚的にわかりやすくて◎。
家の中でできる活動アイデア
ひとり時間でも楽しめて、学びや成長にもつながる活動をご紹介します。
◎ 自宅学習
学校の宿題
市販のドリルや知育プリント
学習アプリ(時間制限ありで活用)
◎ 創作活動
お絵描き・工作・ぬりえ
折り紙・あやとり
簡単な日記や絵日記をつける
◎ お手伝いタイム
洗濯物をたたむ
植物に水をあげる
おやつを自分で準備する
「これをしたらシールを貼る」といったチャレンジ表もモチベーションにつながります。(参照:トークンシステムで子どものモチベと自信アップに)
日替わりで『今日の課題(本を1冊読む、好きな動画の好きなところを文章する、大きな紙に絵を描くなど、普段しないようなことで、成果を発表できるもの)』を決めて、親・保護者が帰宅したら、課題の成果を報告するというのも面白いかもしれません。
月を作る!?\ https://amzn.to/43MTymL /自由研究にもオススメ
外出する場合のルールも明確に
外に出ることを許可する場合は、必ず「いつ」「どこまで」「何時まで」といったルールを決めておきましょう。
▶近所の公園に30分だけ
▶児童館や図書館で過ごす
▶地域の子どもイベントに参加する
安全面が心配な場合は、GPS付きのキッズケータイや見守りアプリの活用もおすすめです。
親・保護者と連絡が取れる場合は、外出するときは連絡を入れてもらうようにするといいですね。
安全面のポイント
低学年の子が一人で過ごす場合、下記のようなルールを事前に確認しておくことが大切です。
⚠火・水・刃物などは使わない
⚠知らない人を家に入れない
⚠緊急時の連絡先をわかる場所に貼っておく
⚠鍵のかけ忘れや戸締まりの確認
特に1年生のうちは、「できること」と「できないこと」の線引きを親子でしっかり共有することがカギになります。
仕事の合間に子どもに連絡して様子を聞いたり、こまめにメッセージを送れると、子どもも安心できるでしょう。「○時と△時になったら連絡してね」など、定期的に連絡を入れてもらうようにするのも一つの手です。
また、「今このお仕事をしてるよ」と学校日ではできない連絡をすると、子どもにとっては新鮮かもしれません。
お役立ちグッズ紹介
↓「GPSは欲しいけど、ケータイを持たせるのはちょっとまだ…」そんな方におススメ。
子どもが使うことに特化していて、ボイスメッセージも送れる機能つき。複雑な操作は必要なく、バッテリーも長持ち。低学年の子どもでも簡単に使うことができます。
↓コスパで選ぶならこれ。(android専用)
子どもだけでなく、お年寄りや荷物の紛失防止にも使えます。
さいごに
夏休みの「一人の時間」は、子どもにとって大きなチャレンジでもあり、成長のチャンスでもあります。
「自分のことは自分でやってみる」「時間を守る」「家で安全に過ごす」──こうした経験が、子どもに自信を与えてくれます。
もちろん、子ども一人にすべてを任せるのではなく、サポートの手を残しながら“見守る”姿勢が理想です。
「何をしたか」「どんな気持ちだったか」を親子で話し合う時間も、夏の思い出になりますように。
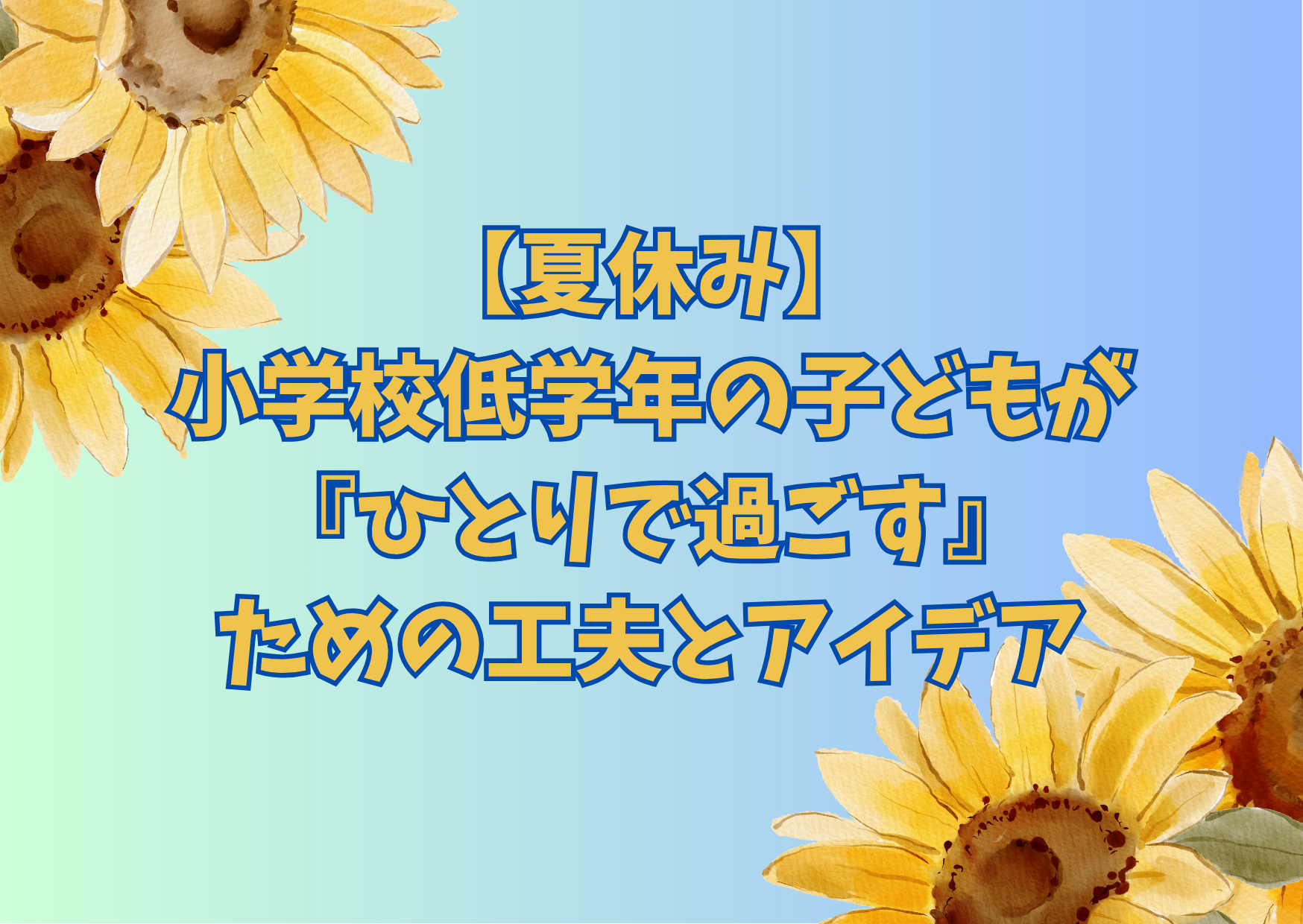
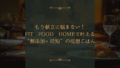
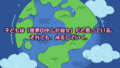
コメント