ジャン・ピアジェ(Jean Piaget)は、スイスの心理学者であり、生涯を通じて「子どもはどうやって考えるようになるのか?」という問いを追求しました。
彼は子どもに質問を投げかけたり、観察したりすることで、子どもの思考が大人とは根本的に異なると気づきました。
ピアジェが考えた4つの発達段階について、それぞれ紹介・解説していきます。
最近、うちの子がやたらと理屈っぽい…。
「これとこれは一緒じゃない!」とか「ルールだからダメ!」とか、なんだか“かたくな”に感じること、ありませんか?
でも実はそれ、発達のサインかもしれません。
今回は、ピアジェの発達理論でいう【具体的操作期】にあたる子どもたちの思考の特徴と、親としての関わり方をご紹介します。
具体的操作期とは?
ピアジェによれば、7歳ごろから子どもは「見たまま」だけでなく、実際の経験やルールをもとに“筋道立てて考える力”が育ってきます。
つまり、「目に見えるもの」に基づいて、具体的に論理的に考えることができるようになる段階です。
この時期の特徴3つを紹介していきます。
小学校に上がったら\ https://amzn.to/4raIlX7 /UNO!
❶ 保存の概念が理解できるようになる
前操作期では「コップの形が変わったら水の量も変わる」と考えていた子が、
この時期になると「形が変わっても量は同じ」と理解できるようになります。
これは「保存の概念」と呼ばれ、論理的思考の始まりを示す大きなステップです。
❷ 物事を分類・順序づけできるようになる
たとえば、「この花は赤いけどチューリップ」「この花は黄色でチューリップじゃない」など、
複数の視点から物を見分けたり、順序づけたりする力が育ってきます。
🔸例:
・色別に分ける
・大きさ順に並べる
・数字の大小を理解する
❸ 脱自己中心性
この時期の子どもは、自分と他人が違うことを理解し始めます。
「自分が見ている世界と、相手が見ている世界は、一緒ではない」と気づくようになります。
他の人の視点を考えたり、自分とは違う気持ちに共感することができるようになるため、自己中心的な考えが少なくなっていきます。
親にできる関わり方
☑「理由」を大切にする
子どもが何かにこだわっていたら、「なんでそう思ったの?」と理由を聞いてあげることがポイントです。
納得できる理由があれば、自信を持って判断できるようになります。
☑ 話し合いでルールを決める
「これはこうだからダメ!」と頭ごなしに否定せず、ルールを一緒に決める経験を通じて、柔軟な思考も育ちます。
🔸例:「ゲームは〇分まで」「宿題をしてからYouTube」など、話し合いながらルールづくり。
☑ 遊びや体験を通して学ぶ
この時期の子は、抽象的な話より実体験を通した学びが響きます。
🔹おすすめ:お金の計算を使った買い物ごっこ、カードゲームで順序や論理のルールを学ぶ、自然観察・実験キットで因果関係を体感する など
お役立ちグッズ紹介
↓家族全員で楽しめるボードゲーム。
知育玩具としても優秀で、ルールは簡単。一家に一つあると盛り上がります。
↓論理的思考といえばプログラミング。
小学生を対象にしたプログラミング教室で、オンラインでもしっかりと学習できる仕組みがあります。
プログラミング初心者でももちろん歓迎。自分で考える力をつけさせたい人にオススメです。

さいごに
「理屈っぽい」=考える力が育っている証拠。
具体的操作期の子どもは、「なんで?」「どうして?」「それはルールに合ってる?」と、筋道立てて考えたがる時期。
一見「生意気」「かたくな」と感じる場面も、
実は“考える力”“正義感”“論理性”が育っている大切な時期なんです。
親としては、「めんどくさいな…」と思う瞬間もあるかもしれません。
でも、子どもの主張に耳を傾け、理由を一緒に整理していくことで、子どもは自分の考えをもつ力と、人と向き合う力を身につけていきます。

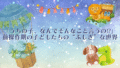
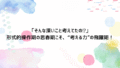
コメント