ジャン・ピアジェ(Jean Piaget)は、スイスの心理学者であり、生涯を通じて「子どもはどうやって考えるようになるのか?」という問いを追求しました。
彼は子どもに質問を投げかけたり、観察したりすることで、子どもの思考が大人とは根本的に異なると気づきました。
ピアジェが考えてた4つの発達段階について、それぞれ紹介・解説していきます。
「水の量は同じなのに、“こっちのコップのほうが多い!”と主張する」
「“昨日、お月さまとお話したよ”って…え?まさかのファンタジー⁉」
2~7歳ごろの子どもって、発想が独特で面白いですよね。
大人には理解しがたい“ふしぎ発言”の数々。でも、それにもちゃんと理由があるんです。
今回はピアジェの発達理論から、この時期の子どもたちの思考の秘密に迫ります。
前操作期とは?(2〜7歳ごろ)
スイスの心理学者ピアジェは、人の思考が段階を経て発達していくと提唱しました。
前操作期はその第2段階で、言葉を使えるようになり、想像力もぐんと広がる時期です。
でもこの時期、まだ「論理的に考える力」や「相手の視点に立つ力」が未発達。
それが“ふしぎ”な言動や、思わず笑ってしまうような発言につながっているんです。
グッド・トイ受賞の知育玩具\ https://amzn.to/4pg6k69 /
この時期の特徴は?キーワードは「自己中心性」
❶ 自己中心性(egocentrism)
前操作期の子どもは、まだ“他の人の気持ち”や“視点”を考えるのが苦手です。
🔸例:「ママが見てなくても、ぼくが見てるからOK!」
これは「自分が見てる=ママも見てる」と思っているということ。
「わざとじゃないのに、なんで謝らないの!?」と大人がイライラすることも、
子どもはそもそも“相手の気持ちに気づく力”がまだ育っていないだけ、ということもあります。
❷ 見た目に惑わされる(保存の概念が未発達)
同じ量のジュースでも、細長いコップに入れると「こっちの方が多い!」と言う子。
これは、「見た目=そのまま現実」と捉えてしまうから。
ピアジェはこの現象を通して、「保存の概念」(見た目が変わっても量は同じ)がまだ理解できていないと考えました。
❸ 空想と現実の境界があいまい
「妖精が来て、おもちゃ片づけてくれた」
「お月さまがぼくの話を聞いてくれた」
大人には“ウソ”に聞こえる発言も、この時期の子にとってはリアルでまじめな話。
空想と現実の境目がまだあいまいで、想像力がのびのびと働いている証拠です。
親にできる関わり方
☑「なんで?」攻撃には付き合ってOK!
この時期はとにかく「なんで?」「どうして?」が止まりません。
これは言葉の発達と知的好奇心のあらわれ。
すべてに正しく答えようとせず、「一緒に考える」姿勢でOKです。
☑ 自己中心的な言動には「責めずに伝える」
「相手の気持ちを考えてごらん」と言っても、すぐには難しいことも。
「ママはこう感じたよ」「お友だちはこうだったかもね」と、相手の気持ちを翻訳して伝えるようにしましょう。
☑ ごっこ遊び・空想遊びをたっぷり
この時期の遊びは、ただの“おふざけ”ではなく「心と頭のトレーニング」。
ごっこ遊びを通して、言葉・感情・想像力をどんどん育てていきます。
人気のお医者さんごっこセット\ https://amzn.to/480m332 /
お役立ちグッズ紹介
↓木製のおままごとセットや、知育玩具も豊富。
おもちゃの内部に磁石が入っているため、マジックテープより長持ち&安全。子どもが持ちやすい形や色にこだわりながらも、食材のリアルなデザインで、子どもの探求心をくすぐってくれます。
↓ただの図鑑じゃない、知育図鑑もオススメです。
音が出るタイプは目でも耳でも楽しめて、タッチペンで「押す」感覚も育てられます。
日本語と英語の両方が収録されているので、学習教材としても優秀です。
まとめ:子どもは“ちいさな研究者”
前操作期の子どもは、見るものすべてが不思議で、考えることすべてが実験です。
「なんでそう思ったの!?」と驚く言動も、彼らなりに一生けんめい「世界のしくみ」を理解しようとしている証。
大人にはちょっぴり面倒でも、子どもの目線に立ってみると、その世界はとても自由で、面白くて、温かい。
「これは“前操作期”だからなんだな」と、少し視点を変えるだけで、子どもとの関わりがもっと楽しくなるかもしれませんよ。


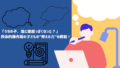
コメント