ジャン・ピアジェ(Jean Piaget)は、スイスの心理学者であり、生涯を通じて「子どもはどうやって考えるようになるのか?」という問いを追求しました。
彼は子どもに質問を投げかけたり、観察したりすることで、子どもの思考が大人とは根本的に異なると気づきました。
ピアジェが考えてた4つの発達段階について、それぞれ紹介・解説していきます。
赤ちゃんって、なんでも口に入れたがりますよね。
ティッシュ、リモコン、自分の足…「ちょっとやめてー!」と思う反面、それも実は、ちゃんと意味がある行動なんです。
今回は、スイスの心理学者ジャン・ピアジェが提唱した「感覚運動期」の視点から、赤ちゃんの世界をちょっとのぞいてみましょう。
お手入れ簡単の歯固め\ https://amzn.to/47VazxE /
感覚運動期とは?(0〜2歳ごろ)
ピアジェによると、人の思考力は段階的に発達していくと言われています。
その最初のステージが「感覚運動期」。生まれてから2歳ごろまでがこの段階です。
この時期の子どもは、「見る・聞く・触る・なめる・動く」など、自分の五感と身体の動きを使って世界を理解していきます。
大人にとっては「あたり前」のことも、赤ちゃんにとっては毎日が新発見!
たとえば、ガラガラを振ると音が鳴る → 「あ、ぼくが振ったら音がした!」という“因果関係”を学んでいるんです。
「なんでも口に入れる」の理由
この時期の赤ちゃんは、【口が第2の目】とも言えるくらい、口で物を確認します。
それは、ただのクセや困った行動ではなく、五感をフル活用した学びの一環。
実はこの時期、まだ「目で見るだけでは“それが何か”を理解する」ことができません。
触ったり、なめたりして、ようやく「これは柔らかい」「冷たい」などの感覚がわかるのです。
「対象の永続性(モノの永続性)」の発達とは?
もうひとつ、この時期の大きな発達の特徴が「対象の永続性」の獲得です。
これは、「物が見えなくなっても、存在し続けている」と理解できる力のこと。
生まれたばかりの赤ちゃんは、目の前から物が消えると「もうない」と思いがち。
でも、成長とともに「隠れててもあるよね」と気づくようになります。
「いないいないばあ」に赤ちゃんが大喜びするのも、この“永続性”が発達していく過程なんです!
親・保護者ができること・関わり方
この時期は、「たくさん触って・たくさん遊ぶ」が学びになる時期です。
難しい知育なんて必要ありません。シンプルなおもちゃでOK!
▶いないいないばあ、くすぐり遊びなどの反応遊び
▶握ったり舐めたりできるシンプルなおもちゃ(布のおもちゃ、歯固めなど)
▶抱っこしながらお話しする(言葉のシャワーが脳を育てます)
「いつも同じ遊びでいいのかな?」と不安になるかもしれませんが、赤ちゃんは“繰り返し”を通して理解を深めていきます。
お役立ちグッズ紹介
↓布絵本や木のおもちゃなど、感覚運動期にぴったりのおもちゃがたくさんあります。
商品を眺めるだけでも楽しくなります。ギフトにもぴったりです。
確かな知育効果・知育玩具のGENI[ジェニ] by エドインター
さいごに
赤ちゃんが何でも口に入れたり、同じことを何度も繰り返したりするのは、すべて「世界を知りたい!」という純粋な探求心から来ています。
大人の目には“意味がない”ように見えても、実はひとつひとつが、確実に「考える力」へとつながっているんですね。
「今は“感覚運動期”だからこそ必要な遊びなんだ」
そう思って、安心して赤ちゃんとの毎日を楽しんでくださいね。
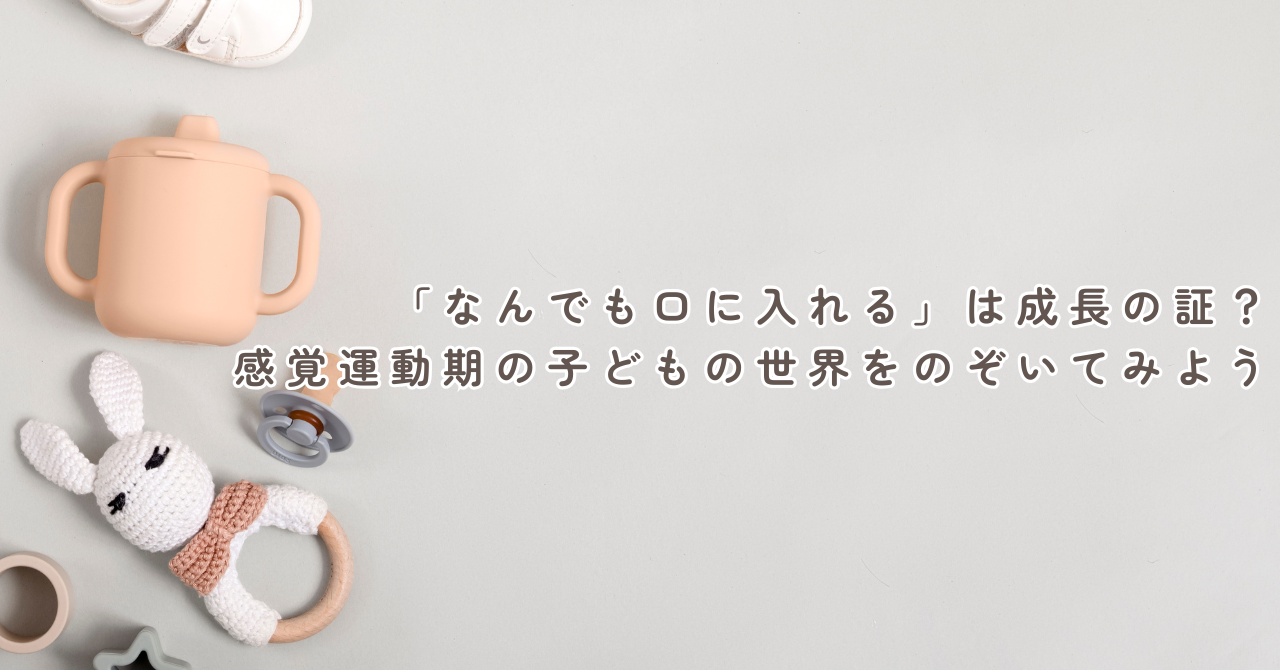
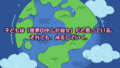

コメント