【本日のお悩み】
○子どもがどうしても字をうまく書けない
○計算があまりにも苦手すぎる
○簡単な文章でも読めない
お悩み解消ヒント:それ、本人の努力不足ではないかも
知的な遅れは見られないのに、特定の分野だけかなり苦手……それ、もしかしたらLD(学習障害)かもしれません。
LD(学習障害)とは
LDとは、Learning disabilities(Learning difference)の略称で、文部科学省や世界的な疾病分類でも定義されている障害です。
学習障害とは、全般的に知的発達に遅れはないが、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」といった学習に必要な基礎的な能力のうち、一つないし複数の特定の能力についてなかなか習得できなかったり、うまく発揮することができなかったりすることによって、学習上、様々な困難に直面している状態をいいます。
(文部科学省HPより引用)
誤解と偏見がまだまだ多い
LDは本人の怠惰や努力不足ではなく、中枢神経系に発生した何らかの機能障害が原因とされています。他の障害や環境的な要因は、LDの直接の原因ではありません。
ただ、LDは特定の分野以外の能力には問題がないため、本人の努力不足だと誤解されがちです。
「字がうまく書けないから、ひたすら文字を書かせる」「文章が読めないから、読めるまで何度も音読させる」こういった指導が日常的に行われてしまうと、子どもは疲弊し、問題のなかった能力すらも発揮できなくなるかもしれません。
うつ病や適応障害、不登校といった二次障害が起こる可能性もあります。
LDに必要なのは、適切な支援と環境なんです。
読み書きの支援ならこの本\https://amzn.to/3Kb4OCI/
具体的な方法:専門機関や学校と連携しながら、子どもを伸ばすサポートを
LDにかかわらず、発達障害は早期から支援を受けることが望ましいです。
適切な支援とサポートは子どもの学びにつながり、大人になっても「こういうときはこうすればいいんだ」「困ったときはここに聞けばいい」と、日常生活を快適に送りやすくなります。
LDは小学校入学以降に見つかりやすい
「ひらがなは読めるけど書けない」「計算の手順が覚えられない」「音読が極端に苦手」など、小学校の学習が始まると、LDが発見しやすくなってきます。
保護者が「あれ?」と気づく場合もありますし、学校が「もしかして」と感じる場合もあります。
「あれ?」と思ったら、専門機関へ
LDかもしれないと感じたら、専門機関に相談しましょう。
専門機関はかかりつけの小児科や、精神科・心療内科、児童精神科でも相談できます。
相談先によっては他の専門機関に紹介される場合もあるため、現在の状況などをまとめておくといいでしょう。
診断にはテストがある
LDかどうか診断するため、知能検査やテストが行われることがあります。これはLDの定義に「知的な遅れは見られないが、特定の領域で顕著な遅れがある」とあるからです。
数値化されて低い数字を見てしまうと、保護者の皆さんは落ち込んでしまうかもしれません。「この子の将来はどうなってしまうんだろう」と、絶望してしまう方もいらっしゃるでしょう。
落ち込むことは悪いことではありません。しかし、子どもの将来を考えるのであれば、今から自分にできることを精一杯していく方が、子どものためになりませんか?
悲しんで落ち込んだら、次は子どものためにできることを探していきましょう。
LDと診断されたら、各所と連携
診断を受けたら、まず学校に連絡してください。今後の学習について、子どもに寄り添える環境づくりを相談していきましょう。LD=支援教室とは限りません。通級指導教室といって、今の学級に在籍したまま、一部で特別な指導を受けることもできます。
児童発達支援事業所や放課後等デイサービスなど、学校以外でも支援やトレーニングを受けられる場所はあります。気になったところにはどんどん連絡してみましょう。
親・保護者ができること
①成功体験を増やす
LDを持つ子どもは、特定分野の理解が追いつかず不安になりがちです。失敗したり、他の子と比べて落ち込むことも増えていくでしょう。
小さなことでも、成功体験を積み重ねることは自己肯定感を引き上げてくれます。自己肯定感が上がると自信がつき、その自信が子どもを次のステップに導いてくれるでしょう。
②環境を整える
子どもが学習に集中しやすい環境を、子どもに合わせて作りましょう。
学習の進捗が目で見てわかるようなスケジュールを作ったり、タイムタイマーの活用、図解の作成や、音声の使用など、アプローチ方法は様々です。
子どもの「できる」を伸ばしつつ、苦手分野にも挑戦できるような環境にしていけるといいですね。
おすすめの書籍
↓さまざまな実例や当事者の話など、LDの理解をわかりやすく深めるのにオススメです。
さいごに
LDは、子どもが一番しんどい思いをしています。困っているのは大人ではなく、子ども自身です。
だからこそ、周りの大人は理解とサポートをしていかなければなりません。
子どもを「できる・できない」で見るのではなく、子どもの「強み」に目を向けてサポートしていきましょう。
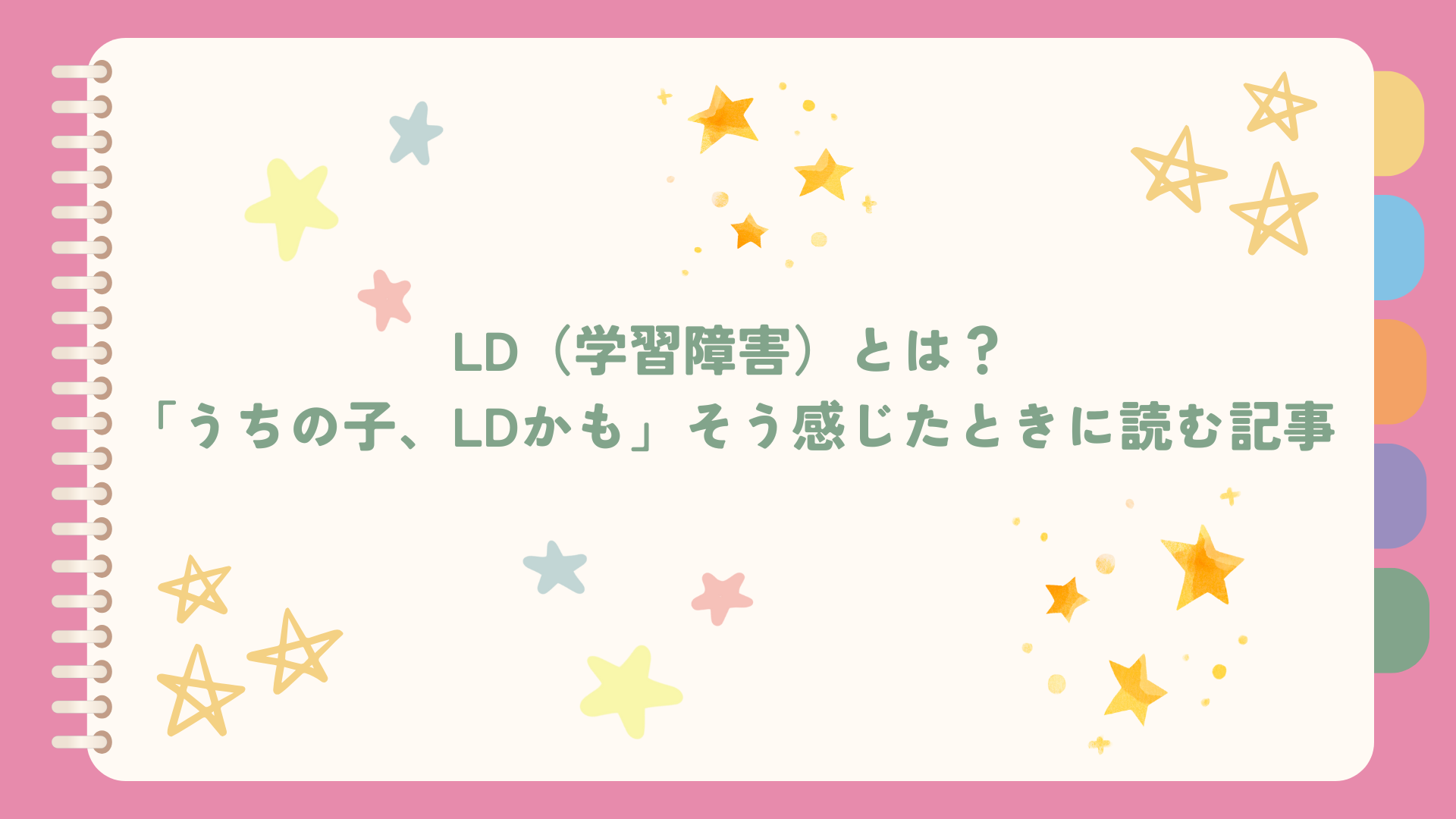


コメント