【本日のお悩み】
○「視覚的支援」とか聞くけど、具体的にどうしたらいいの?
○特別な支援って、障がいがある子だけに有効なんでしょ?
○支援者・児童指導員として、基礎的な知識を知っておきたい
「構造化」って知っていますか?
「構造化」とは、子どもが「何をすればいいのか」「どうすればいいのか」「いつ終わるのか」をわかりやすく伝えるために、環境や活動を整理・工夫することを指します。
もともとは、自閉スペクトラム症などの発達障がいのある子どもたちへの支援として生まれた考え方ですが、実はこれ、未就学児~小学生にも効果的なんです。
例えば、こんな工夫が「構造化」です
- 宿題をやる机の上に、やるものだけを出しておく
- 「今→次→その次」の流れを紙に書いて貼る
- おもちゃの片づけ場所に写真ラベルを貼っておく
- 時計の横に「この色が終わったら片づけ」マークを貼る
こうした工夫をすることで、子どもは「見てわかる」「先が読める」「自分でできた」という体験がしやすくなります。
ソーシャルスキルを遊んで学ぶ\ https://amzn.to/487ePdD /
「構造化」は、発達に関係なく有効!
発達障がいのある子にとっては「見通しが立たないこと」が大きな不安やパニックの原因になります。
構造化はそれをやわらげる有効な方法として活用されてきました。
でも実際には、
- 忘れ物が多い子
- 気が散りやすい子
- 朝の準備に時間がかかる子
- 予定の変更に弱い子
……こうした子どもたちにも、とても有効です。
実は、子ども全体の「やる気」や「自立」を引き出すツールとして、家庭や学校でもどんどん活用されているんです。
子どもが「わからない」ときにこそ、構造化
大人は「説明すればわかる」と思いがちですが、子どもは言葉だけでは理解しづらいことも多いものです。
とくに低学年の子や、慣れない場面、疲れているときなどは、パニックや癇癪につながることもあります。
そんなときに、「見てわかる」「すぐに理解できる」工夫=構造化があると、子どもは安心し、自信を持って行動できます。
まずは家庭で、できることから
構造化は、何か特別な支援ツールを用意しないといけないわけではありません。
たとえば…
- 予定をホワイトボードに書いておく
- 宿題の「順番リスト」を作って机に貼る
- 使うもの・使わないものを仕分けて収納する
こうしたちょっとした工夫からでも、子どもがぐんと過ごしやすくなります。
お役立ちグッズ紹介
↓環境を構造化させるときに役立つアイデア集。
実際の写真や画像が見れるので、イメージも湧きやすいです。こちらは個別に特化した内容なので、放デイなど集団活動が多い場所での構造化は、こちらも参照してみてください。
さいごに
構造化は、子どもをコントロールするためのものではなく、子どもが「自分でできた!」と思えるためのやさしい仕掛けです。
どんな子にもわかりやすく、安心して、自分らしく過ごせるように。
ぜひ、家庭でも取り入れてみてくださいね。

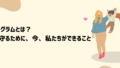
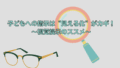
コメント