【本日のお悩み】
○同じことを何度注意しても聞かない
○子どもに社会のルールを教えたい
○子どもが怒られることに慣れてしまっている
お悩み解消ヒント:「○○しない」ではなく…
おすすめ書籍\ https://amzn.to/4rlSoZG /

お店や公園、学校などでも「走らない」「大きな声を出さない」「遠くに行かない」といった注意をしている/聞くことは多いですね。
実はこの注意、子どもにとっては非常にわかりにくい注意なんです。
なぜなら「走らない」と言われても、子どもは「じゃあどうしたらいいの?」と思うから。
「大きな声を出さない」→「どのぐらいの声だったら出していいの?」
「遠くに行かない」→「どれぐらいなら行ってもいいの?」
注意書きとして良く見られる「工事中。危ないのでここで遊ばないでください」という看板も、「ここで遊んじゃだめなのはわかった。だからここで座っておしゃべりしよう」という解釈をする人がいてもおかしくありません。
「〇〇しない」という言い方は、受け手の解釈によってかなり違ってくるんです。
具体的な方法:「○○しよう」
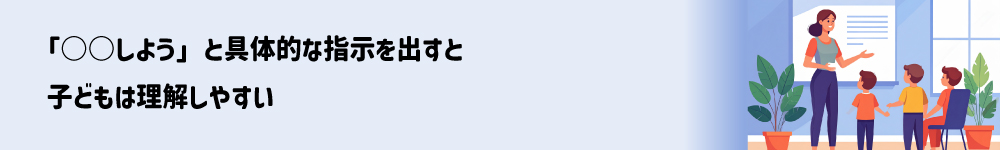
「〇〇しない」から「△△しよう」に言い換えると、子どもにとってはわかりやすいです。
▶「走らない」→「お店の中は歩こう」
▶「大きな声を出さない」→「ここは静かにする場所だから、お話しするときはこのくらいの声で話そう」
▶「遠くに行かない」→「あのすべり台までは行っていいよ。すべり台から先に行きたいときは教えてね」
これは『肯定的声かけ』と言われていて、子どもにとってほしい行動を具体的に伝えることで、子どもの理解を深めてくれます。
児童指導員としての失敗談
この本、読んでおけばよかった……\ https://amzn.to/4ogAW6b /

まだ私が児童指導員になりたての頃、しょっちゅう「部屋の中は走らない!」「静かにする!」「ごはん食べてるときは立たない!」と怒っていました。
今になって思うと、子どもにとって分かりにくい指示ばかりですよね。
何度「走らない」と言っても走りまくる子どもに、試しに「歩いて遊ぼう。走るとお友達にぶつかって危ないからね」と言ってみたんです。
すぐ歩きました(笑)。
こんなに効果が違うのかと、びっくりしました。怒るのにもエネルギーが必要ですし、「○○しよう」で効果が出るなら、こっちの方がいいですよね。
最初はどうしても否定的な声かけになってしまう…でも大丈夫!
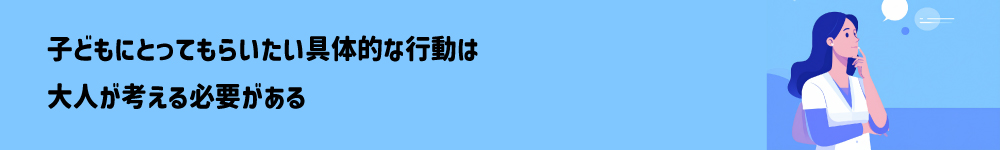
ただ、この肯定的声かけ、実践するとなるとかなり難しいです。注意しようとすると、どうしても「〇〇しないで」という否定的な声かけが先に浮かんでしまうんです。
なぜなら、肯定的な声かけは考えないといけないから。否定するのは簡単だけれども、子どもにとってもらいたい具体的な行動となると、大人が考えないといけません。
こればかりは訓練が必要で、似たような場面を繰り返し体験するしかないと思います。
さらに社会のルールは曖昧なものも多いため、その都度根気強く説明していく必要も出てくるでしょう。
わからないときは正直に「わからない」と伝えて大丈夫です。変に誤魔化すよりも「今は説明が難しいから、あとで一緒に考えよう」「説明できるようになったら説明するね」と言ってください。
お役立ちグッズ紹介:リフレーミング
「言い換える」という手法は、リフレーミングとも呼ばれています。
このリフレーミング、人とコミュニケーションを取るうえでも、自己分析をするうえでも役立つので、気になる方はリフレーミングの本を探してみてください。
リフレーミング導入がわかりやすい/
子どもと接する職業の方におすすめ/
さいごに
肯定的な声かけは、実は私も苦戦しました。
言葉というのは意識しないと変わりません。でも24時間365日意識し続けるというのも疲れてしまいます。
気づいたときでも大丈夫なので、少しずつ意識して変えていけるといいですね。
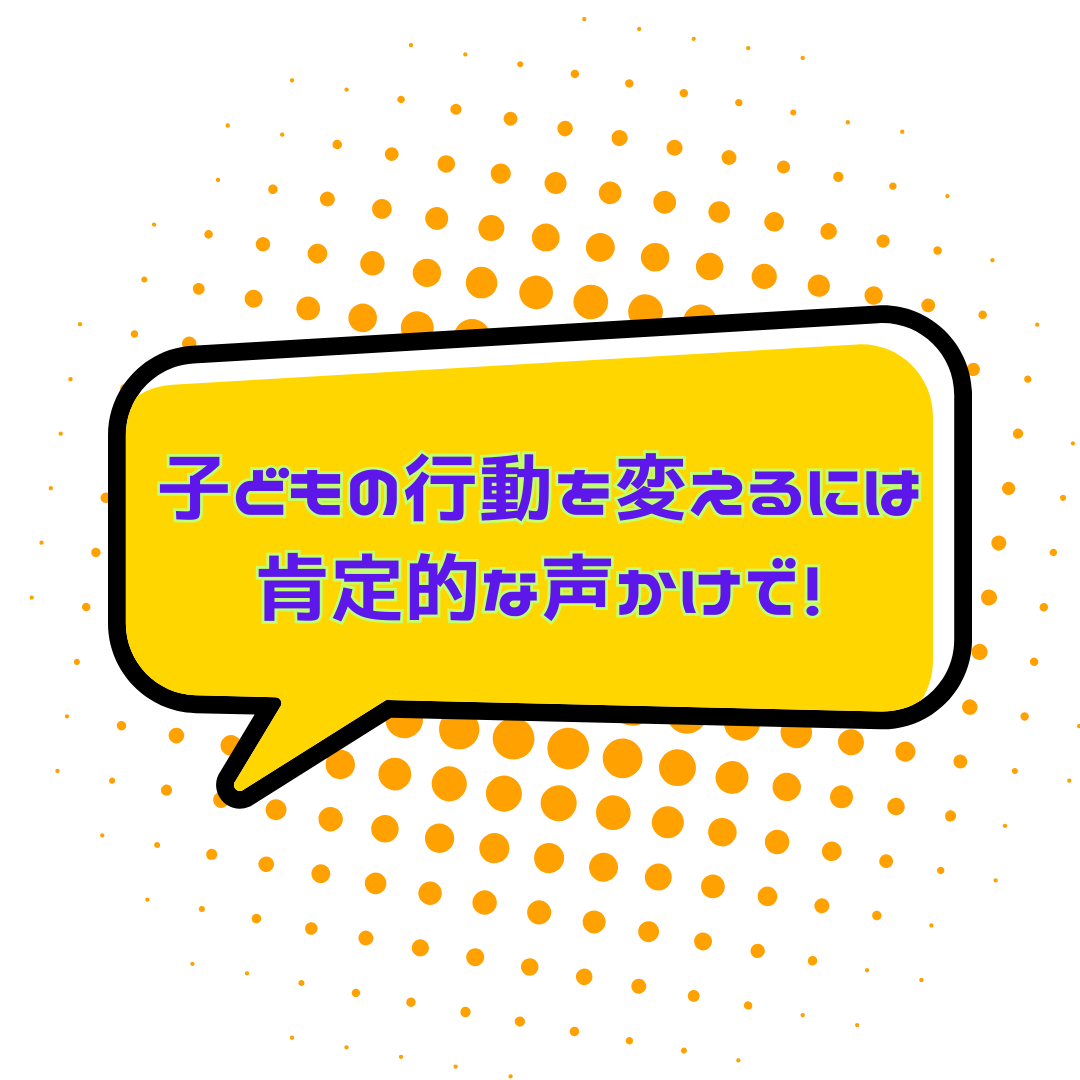

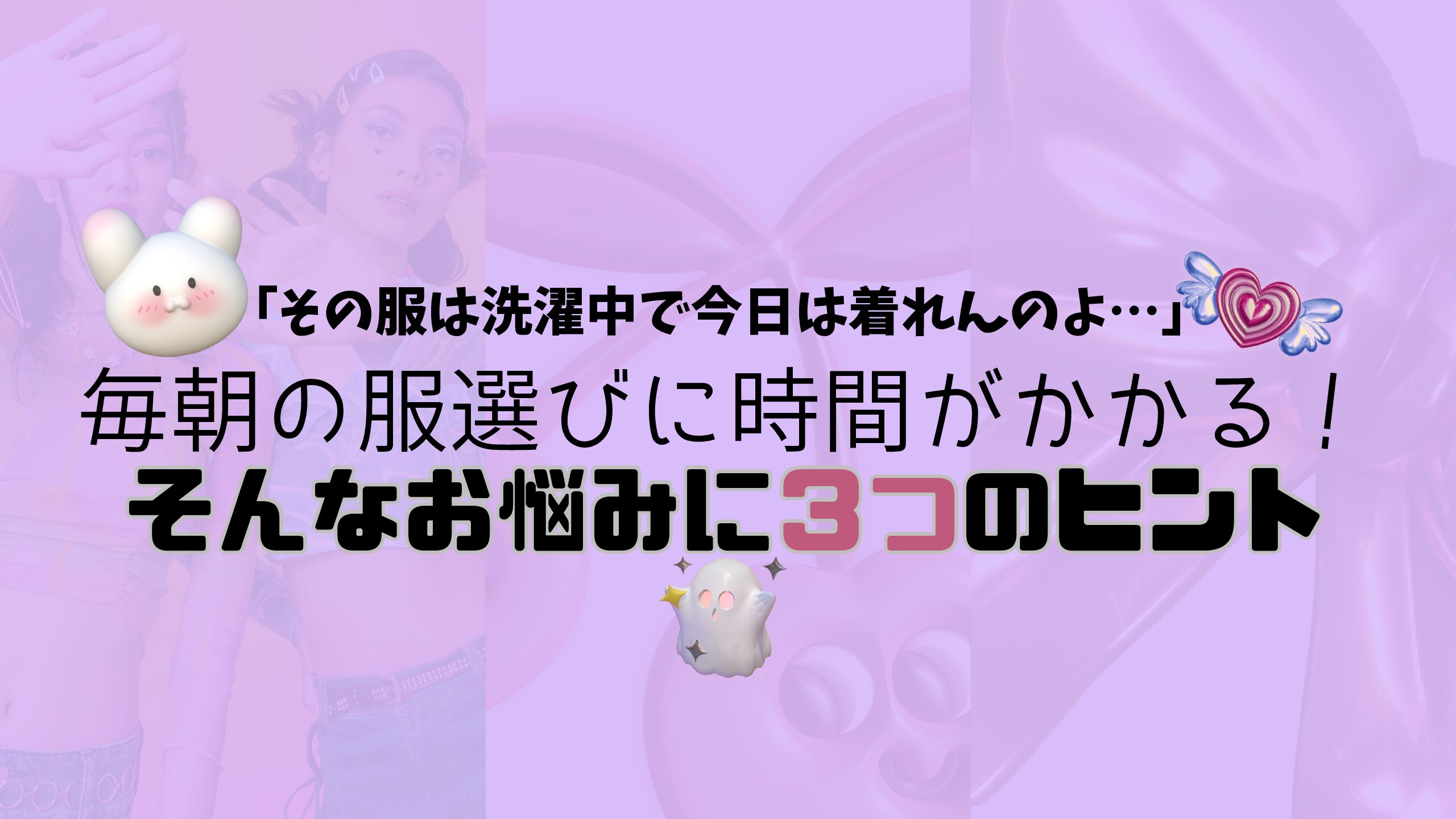
コメント