【本日のお悩み】
○子どもと接する仕事をしているが、子どもとの会話が盛り上がらない
○子どもの話が理解できない
○どうやって子どもの話を聞けばいいかわからない
お悩み解消ヒント:子どもが「聞いてもらえた」と思える姿勢
大人との会話と違い、子どもとの会話はかなり特殊です。
子どもは言葉のキャッチボールが上手ではないことに加えて、語彙も少なく、さらに自分が見えた世界で話を進めていきます。
床に水がこぼれたら、海になる…?
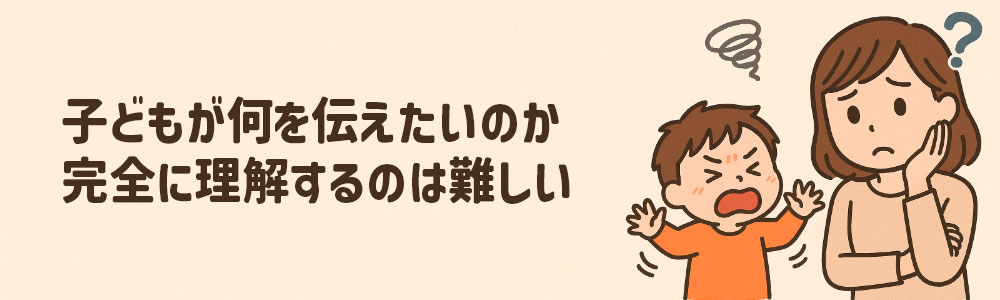
例えば、テーブルに置いていたコップを飼い猫が倒して、床に水がこぼれたという場面。
大人であれば「うちの猫がテーブルのコップ倒しちゃって、床が水浸しになって大変だったんだ」と伝えることができます。
が、子どもの場合は「みーちゃんがね、ちょいちょいして海ができたの。海はきらきらしてきれいでしょ」というように、ともすれば夢やゲームの話かと勘違いするような内容になってしまいます。
でも子ども本人にとっては、
・飼い猫はみーちゃんという名前
・猫が手招きする様子は普段からちょいちょいと呼んでいる
・床に広がった水は海みたいだった
・照明が水に映ってきらきらしてるように見えた
こういった内容を伝えたかったのかもしれません。
子どもが独自の世界観で話しているわけですから、真正面から話を聞こうとしても、完全に理解するのは難しいでしょう。
さて、理解できない話を聞くコツはあるのでしょうか。
具体的な方法:話の内容を復唱して、聞いていることをアピール
大人もそうですが、子どもは自分の話を聞いてくれる相手に話をしたいものです。
そのため、まずはこちらが「あなたの話を聞いていますよ」とアピールする必要があります。
キーワードを繰り返す
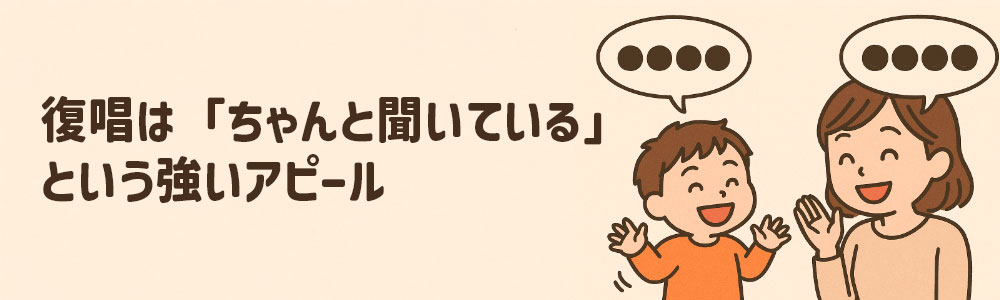
そのアピール方法のひとつが【話のキーワードもしくは話のオチを復唱する】です。
話の内容を理解できなくても、復唱してください。
例えばさっきの例でいくと「みーちゃんがちょいちょいしたんだ(キーワード)」「なるほど、海ができたんだね(オチ)」
また、子どもが「きれいだった」と言っていることから、水浸しの床を好意的に見ていることがうかがえます。子どもの感情が読み取れるときは「きれいな海が見れて嬉しかったね」と、子どもの感情を代弁するのも効果的です。
感情を言語化することで、子どもは「あのときは嬉しかったんだ」と、自分の感情を認識する練習もできるんです。
!!!否定はしない。会話泥棒にも要注意!!!

ここで要注意。
大人が「海ができたって何?海が作れるわけないでしょ」「みーちゃんって誰?誰にでもわかりやすいように説明して」などと、子どもの話を聞かずに頭から否定してしまうと、子どもはもう話したくなくなってしまいます。
また、子どもが「今日お外でこけたけど泣かなかった」と話した際に、大人が「自分も昨日包丁で指切ってさ。かなり血が出て焦ったわ~。見て、まだ傷が残ってる」と、子どもの話から自分(大人)の話に持っていくこともやめてください。会話泥棒ですし、これは大人同士でも印象が悪くなります。
カウンセリングでも話を聞くことは最重要
タイトルも中身もセンス良し\ https://amzn.to/43KHuCu /
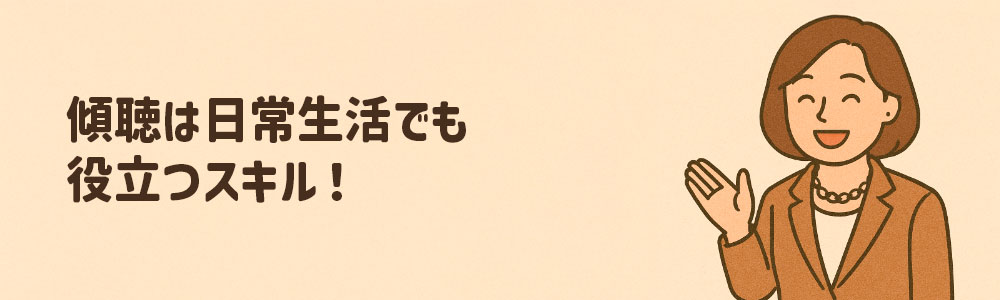
話の内容を復唱したり、感情を言い換える手法は【傾聴】と呼ばれるカウンセリング手法のひとつです。
人と接する仕事をするうえで、相手の話を聞くというのは基本中の基本。特に患者の話から潜在的な悩みや不安を読み取るカウンセリングで、話を聞くことは何よりも重要視されています。
傾聴は心理学の領域でよく聞かれる言葉ではありますが、日常から営業・接客まで幅広く使える手法なので、一度意識してみるのもいいかもしれません。
お役立ちグッズ紹介
傾聴についての本はいくつも出ているので、色々読んで知識を深めていくといいでしょう。傾聴は人間関係の改善にも役立ちます。
さいごに
子どもと話をするときは、子どもが求めない限り聞き手に徹すること。
基本はこの姿勢を忘れないでください。
子どもはおしゃべりしたいんです。覚えたての言葉を間違えて使うこともあるでしょう。そういったときは、子どもが話し終えてから訂正してあげてください。
よほどのことでない限り、子どもの話を遮るのはやめておきましょう。

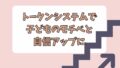
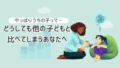
コメント