【本日のお悩み】
○診断はされてないけど、他の子とちょっと違う気がする
○発達グレーゾーンと言われた。どうしたらいい?
○家庭でできる支援方法を知りたい
子育ては日々、喜びと発見に満ちていますが、中には「育てにくさ」を感じたり、周りの子との違いに戸惑ったりすることもあるかもしれません。
発達障害の診断には至らないけれど、集団生活や特定の課題に困難を抱えるお子さんは「グレーゾーン」と呼ばれることがあります。
今回は、家庭で簡単に実践でき、お子さんの自己肯定感を育むための具体的なサポート方法をご紹介します。
ポイント1:「できない」を責めない
子どもが何かを失敗したり、うまくできなかったりしたとき、つい「どうしてできないの?」「ちゃんとやって」と責めるような言葉が出てしまうかもしれません。
しかし、グレーゾーンの子どもにとって、「できないこと」は努力や気持ちの問題ではないことがほとんどです。
⚡️行動の背景にある困難を理解する
- 「片付けができない」のは、何をどこにしまうかの見通しが立たないからかもしれません。
- 「じっとしていられない」のは、感覚の過敏さや、周りの情報を処理しきれていないからかもしれません。
お子さんを責めるのではなく、「今は難しいんだね」と、「できないこと」の裏にある困難に寄り添う姿勢が大切です。
代わりに「どうしたらできそうかな?」と、一緒に解決策を考えるポジティブな声かけに変えてみましょう。
ポイント2:見通しを立てて安心感を与える
次に何が起こるかわからない状況は、子どもにとって大きな不安やストレスにつながります。特に変化に敏感なグレーゾーンの子どもには、見通しを立ててあげることが安心感を生みます。
- 朝に一日の予定を一緒に確認する
- 視覚的にわかりやすいイラストや写真付きのスケジュール(タイムテーブル)を用意し、「朝ごはん→着替え→歯磨き→幼稚園/学校」のように、流れを指差しで確認します。
- 急な予定変更がある場合は、早めに伝え、理由も説明してあげると、心の準備がしやすくなります。
- 終わりの時間を明確にする
- 好きな活動(ゲームやおもちゃ遊びなど)を終えるときには、「あと5分で終わりだよ」とタイマーなどを使って、目に見える形で伝えます。
先のことがわかると、自分で行動を予測し、主体的に動く力が育まれます。
ポイント3:小さな成功体験を積み重ねる
自己肯定感を育む特効薬は、「自分にもできた!」という成功体験です。大きな目標をクリアさせるのではなく、「必ずできること」から始めるのがコツです。
- 細かくステップを分ける
- 「おもちゃを片付ける」を「おもちゃ箱を出す」「ブロックを一つ入れる」「全部しまう」のように、できるだけ小さなステップに分けます。
- 一つクリアするごとに「ブロック、一つ入れたね!すごい!」とすぐに具体的に褒めます。
- 結果ではなく「努力」や「行動」を褒める
- テストで100点を取ったときだけでなく、「机に向かって頑張って勉強したね」「最後まで諦めずに取り組んだね」という過程を評価します。
小さな成功を積み重ねることで、「自分はできる人間だ」という自信が芽生え、次の行動への意欲につながります。
ポイント4:気持ちの逃げ場所(カームダウンスペース)を作る
感情のコントロールが難しいときや、ストレスや刺激でいっぱいに感じたとき、安全に気持ちを落ち着かせられる場所があることは非常に重要です。
- カームダウンスペース(クールダウンスペース)の設置
- 静かで刺激の少ない、家庭内の小さな一角(押し入れの中、テント、大きな布で覆ったスペースなど)を用意します。
- ここはおもちゃなどで遊ぶ場所ではなく、「気持ちを落ち着かせるための場所」であることを明確に伝えます。
- 肌触りの良いクッション、重みのあるブランケット、感覚を落ち着かせるための道具(スライム、ストレスボールなど)、お気に入りの絵本などを置くと良いでしょう。
- ルールは「ここにいる間は誰も詮索しない」
- 子どもがこの場所に行ったら、親は静かに見守り、声をかけすぎないようにします。安全を確保しつつ、気持ちが落ち着くのを待ちましょう。
この「逃げ場所」は、「しんどい時は休んでいいんだよ」という親からのメッセージであり、子どもにとって大きな心の支えとなります。
参考記事→子どもが落ち着ける空間――カームダウンスペースづくり――
さいごに
グレーゾーンの子どもへの支援は、特別なことではなく、「その子の特性を理解し、環境を調整してあげること」です。
「できないを責めない」
「見通しを立てる」
「小さな成功体験を積ませる」
「気持ちの逃げ場所を作る」
これらの4つのポイントを家庭で実践することで、お子さんは安心して生活できるようになり、自立心と自己肯定感をしっかりと育んでいくことができるでしょう。
「グレーゾーン」という言葉に不安を感じるかもしれませんが、それは「その子ならではの個性」を見つけ、適切なサポートをするチャンスでもあります。
完璧を目指さず、親御さんも心にゆとりを持ちながら、お子さんの成長を見守っていきましょう。
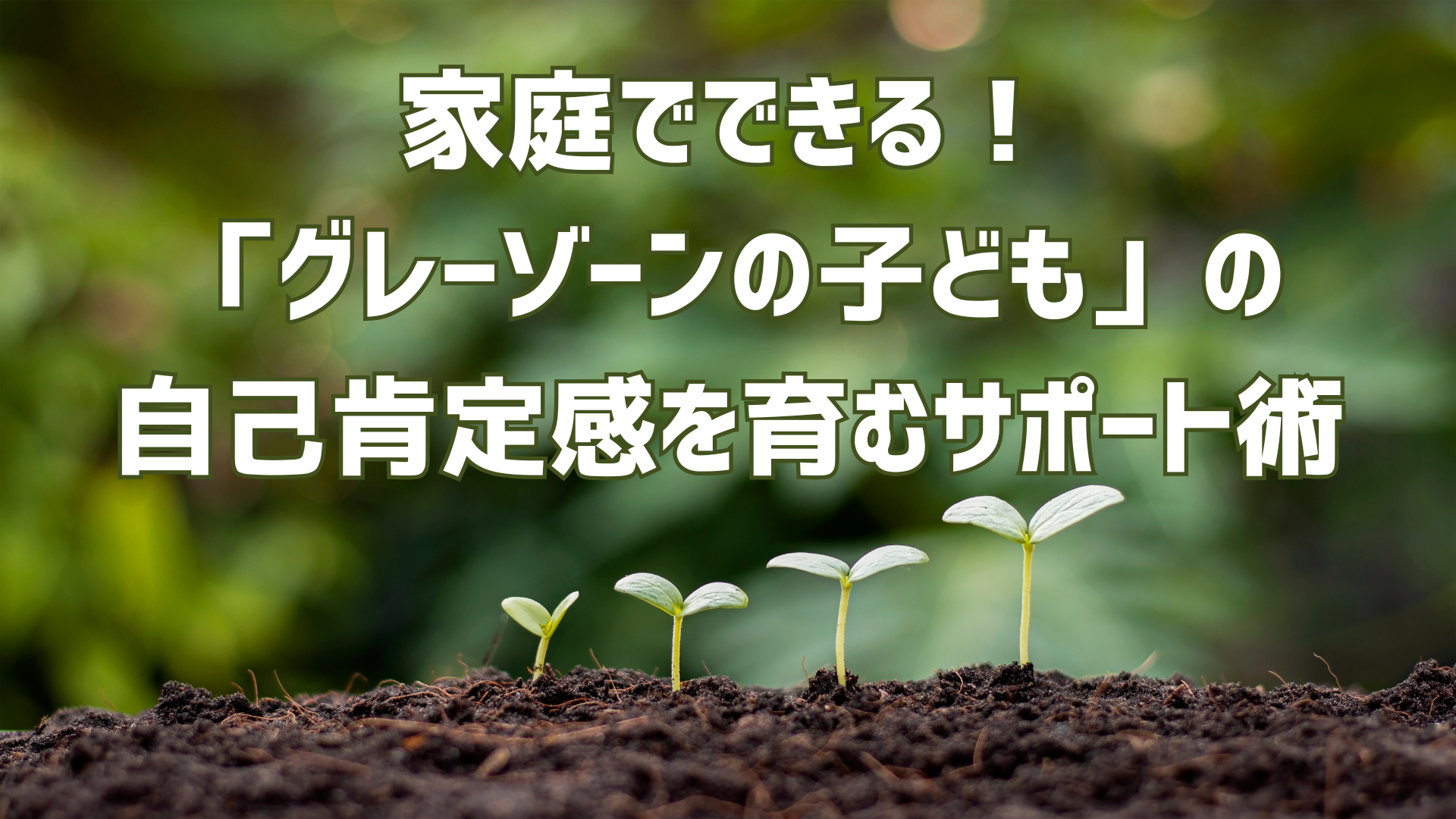
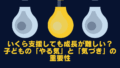
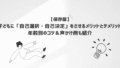
コメント