子どもの不適切な行動を変えたい。良い行動をもっと増やしたい。TPOに応じた行動を取れるようになってほしい。そんな希望が叶うかもしれないアイデアです。
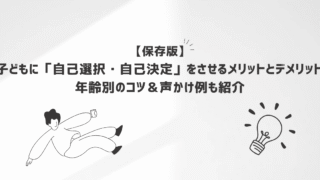 子育てヒント
子育てヒント 子どもに「自己選択・自己決定」をさせるメリットとデメリット|年齢別のコツ&声かけ例も紹介
自分で選び決める力は、主体性や自己効力感を育てる重要スキル。この記事では、子どもの自己選択・自己決定の効果、注意点、家庭でできる取り入れ方を年齢別にまとめました。
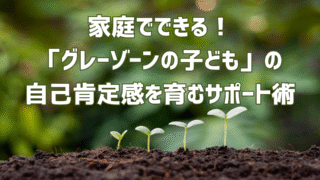 中高生向け
中高生向け 家庭でできる!「グレーゾーンの子ども」の自己肯定感を育むサポート術
【本日のお悩み】○診断はされてないけど、他の子とちょっと違う気がする○発達グレーゾーンと言われた。どうしたらいい?○家庭でできる支援方法を知りたい子育ては日々、喜びと発見に満ちていますが、中には「育てにくさ」を感じたり、周りの子との違いに戸...
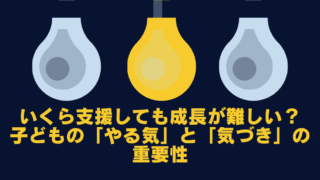 中高生向け
中高生向け いくら支援しても成長が難しい?子どもの「やる気」と「気づき」の重要性
支援の効果が薄い、子どもが成長しない。それは子ども自身に「こうなりたい」という意思が薄いから。あえて子どもに困ってもらう環境を作ることで、子どもの成長を促すことができます。
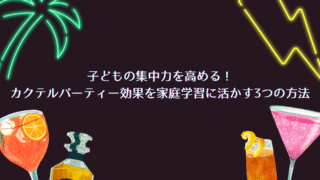 子育てヒント
子育てヒント 子どもの集中力を高める!カクテルパーティー効果を家庭学習に活かす3つの方法
カクテルパーティー効果は、雑音の中でも自分に関係ある情報だけを拾える脳の働き。この記事では、名前を呼ぶ・興味と結びつける・声の工夫という3つの活用法で、子どもの家庭学習を効率化する方法を紹介します。
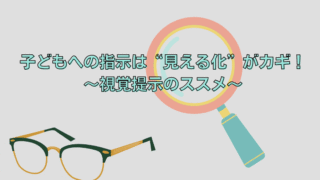 子育てヒント
子育てヒント 子どもへの指示は“見える化”がカギ!~視覚提示のススメ~
「子どもに指示が伝わらない…」と悩んでいませんか?人は情報の約80%を視覚から得ていると言われています。本記事ではその根拠と、子どもへの効果的な視覚提示の方法を具体例つきで紹介します。
 子育てヒント
子育てヒント 子どもが安心して過ごせる「構造化」とは?―発達障がい支援だけじゃない、小学生みんなに役立つ考え方―
「構造化」は発達障がい支援に効果的な方法ですが、実は全ての小学生に役立つサポート術。家庭でも簡単に始められます。
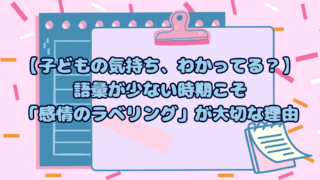 子育てヒント
子育てヒント 【子どもの気持ち、わかってる?】語彙が少ない時期こそ「感情のラベリング」が大切な理由
子どもの感情を代弁する【感情のラベリング】は、子どもの言葉の成長を促します。言葉によって自分の感情を認識し、語彙力を育み、他人の気持ちを考える力も養います。感情のコントロールが苦手な子にもオススメです。
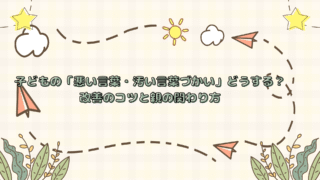 子育てヒント
子育てヒント 子どもの「悪い言葉・汚い言葉づかい」どうする?改善のコツと親の関わり方
悪い言葉づかい・汚い言葉づかいは、子どもが成長していくにつれて発生してくる課題です。家庭の影響や、メディア・SNSの影響もあります。子どもの悪い・汚い言葉づかいを改善するアイデアを掲載しています。
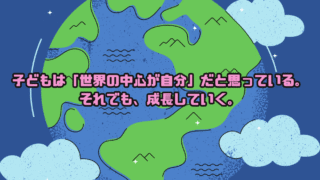 子育てヒント
子育てヒント 子どもは「世界の中心が自分」だと思っている。それでも、成長していく。
幼児期の子どもは、自分が中心。これは自己中心性と呼ばれる、成長過程のひとつ。自分が知っていることは他人も知っていると思ってしまうのも、自己中心性。自己中心性の解説と、大人ができる関わり方について説明。
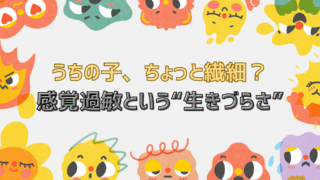 子育てヒント
子育てヒント うちの子、ちょっと繊細みたい…感覚過敏という“生きづらさ”
気にならないような汚れや匂い、特定の光や音といった刺激に、過敏に反応してしまう感覚過敏。感覚過敏の分かりやすい解説と、家庭でできる対応についてまとめました。