【本日のお悩み】
○本を読まない
○文章を読むのが苦手
○算数の文章問題が理解できない
お悩み解消ヒント:文字への苦手意識があるのは仕方ない
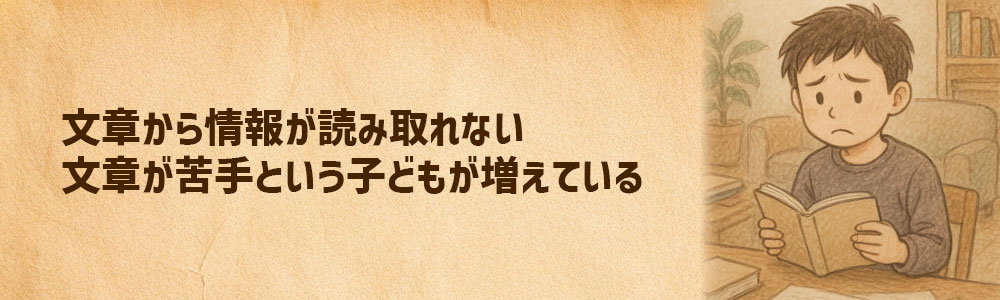
最近は、YouTubeをはじめとした動画が身近になってきました。特にTikTokなどのショート動画は手軽に短時間で視聴できるため、集中力を必要としなくても情報を得ることが可能です。(その情報も玉石混交なので注意が必要ではありますが…)
そのため特性の有無に関わらず、文章から情報が読み取れない・文章が苦手という子どもが増えているようです。
今回は文章が苦手な子どもに向けた工夫をご紹介しますが、文章が苦手な子の中にはLD(学習障害)が潜んでいる場合もあるため、不安に感じた場合は医療機関に相談してみてくださいね。
具体的な方法:読める工夫をして、読み取る力を育てる
文章が読めないと一言で言っても、「読み飛ばしが多い」「読めるけど内容が理解できてない」「読めない文字が多い」など、状況は子どもによってさまざまです。
子どもの様子を見ながら、以下の工夫を試してみてください。
まずは声に出して読む
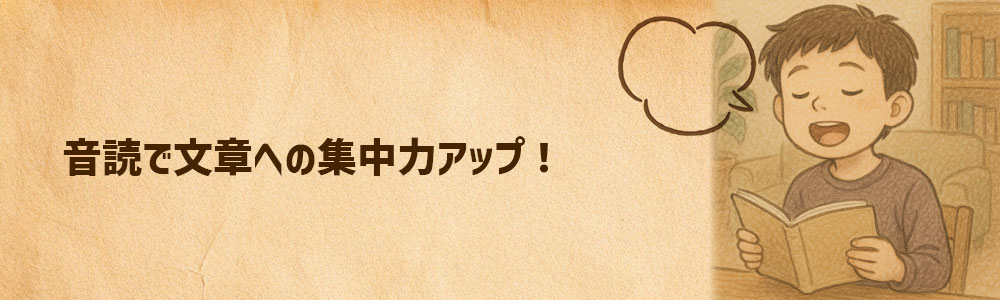
簡単な文章でも、まずは声に出して読んでみましょう。音読ですね。
音読は黙読と比べて、文章に対する集中力が必要になってきます。音読することで読み飛ばしにも気づけますし、読めない文字や苦手な文字の発見があるかもしれません。単語の区切りやイントネーションがおかしいと、その単語が理解できていない可能性もあります。
音読は耳からの情報も入ってくるため、文章理解に大きく役立ってくれる方法です。
(ちなみに、音読だけでもかなりの効果があります。私が勤めている放デイで、算数の文章問題が苦手な子に音読を促したところ、「えんぴつが2本」の問題文を「えんぴつが1本」と思い込んでいたようで、音読したことで「あ、これ2本だ」と気づくことができました👏)
指をあてて読む(+音読)
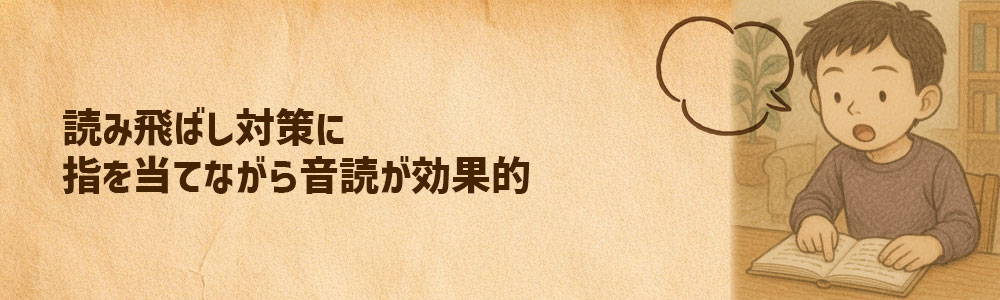
これは読み飛ばしの多い子どもに有効的です。
読むスピードに合わせて指を動かすことができるため、じっくりと文字に集中して読むことができます。
今、自分がどこを読んでいるのか目で見てわかりやすいため、読み飛ばしに気づきやすくなります。
文章の内容を把握するというよりは、まずは文字を知り、文章を読むことに慣れることから始めていきましょう。単語のまとまりも意識できるといいですね。
定規をあてて読む(+音読)
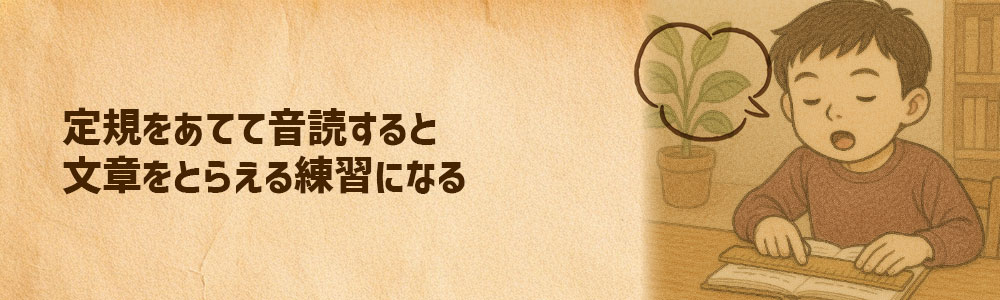
指をあてて読むことに慣れてきたら、今度は文章をまとめて読む練習に入ります。
定規や下敷きなど、まっすぐなものであれば何でも構いません。紙でも大丈夫です。
指をあてて読むときは、一文字一文字に意識を向けることができましたが、定規をあてて読むと一文のまとまりに意識を向けなければなりません。
文字が読めたら次は文章。文字の連なりを文章としてとらえる練習をしていきましょう。
わかる部分を図で描く
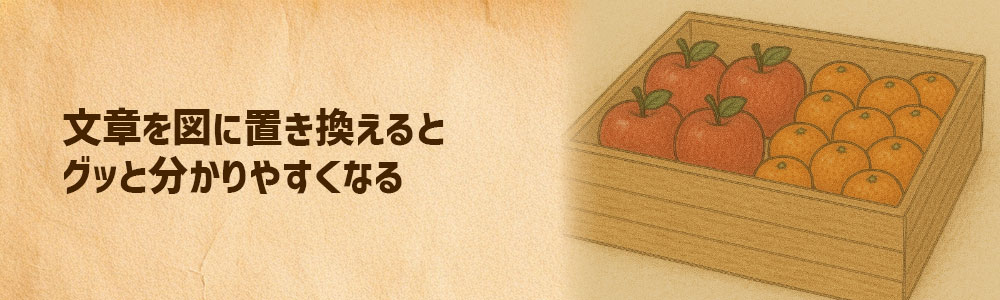
これは算数の文章問題を解くときに活用できます。
理解できる情報を図にすることで、大人はどこにつまづいているのか見てわかりますし、子どもは自分で考える手助けになります。
例えば「箱にりんごが5個、みかんが8個入っています。みかんを3個食べると、箱に残っている果物の数はいくつでしょう」という文章問題。
式にすると5+8-3ですが、数字だけ見て全部足し算にしてしまったり、読み飛ばして5+8だけで終わったりする場合があります。
まずは箱にりんごが5個・みかんが8個入っている図を描く。次に8個のみかんから3個消す。
大人にとっては「これだけのことで」と思うかもしれませんが、文章が苦手な子どもにとっては、十分に多い情報量です。
ひとつひとつ図を描くことは、文章の内容を噛み砕き、理解の促進に役立ちます。
お役立ちグッズ紹介
絵本は、小さい子どもはもちろん、文章が苦手な子どもにも親しみを持ってもらいやすいアイテムです。
文字がない絵本から、読み応えばっちりの絵本まで、選択肢は豊富にあります。是非、たくさんの絵本に触れてみてください。
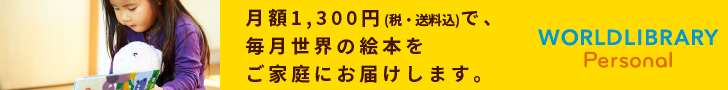
さいごに
絵本やパズルなど、文字に親しむ方法はたくさんあります。
算数の九九を繰り返し言って覚えるように、文字や文章も数をこなしていけば、苦手意識は薄れていくでしょう。
個人的に読書は最高の娯楽のひとつだと思っているので、読書好きな子が増えていくといいなぁと思っています。
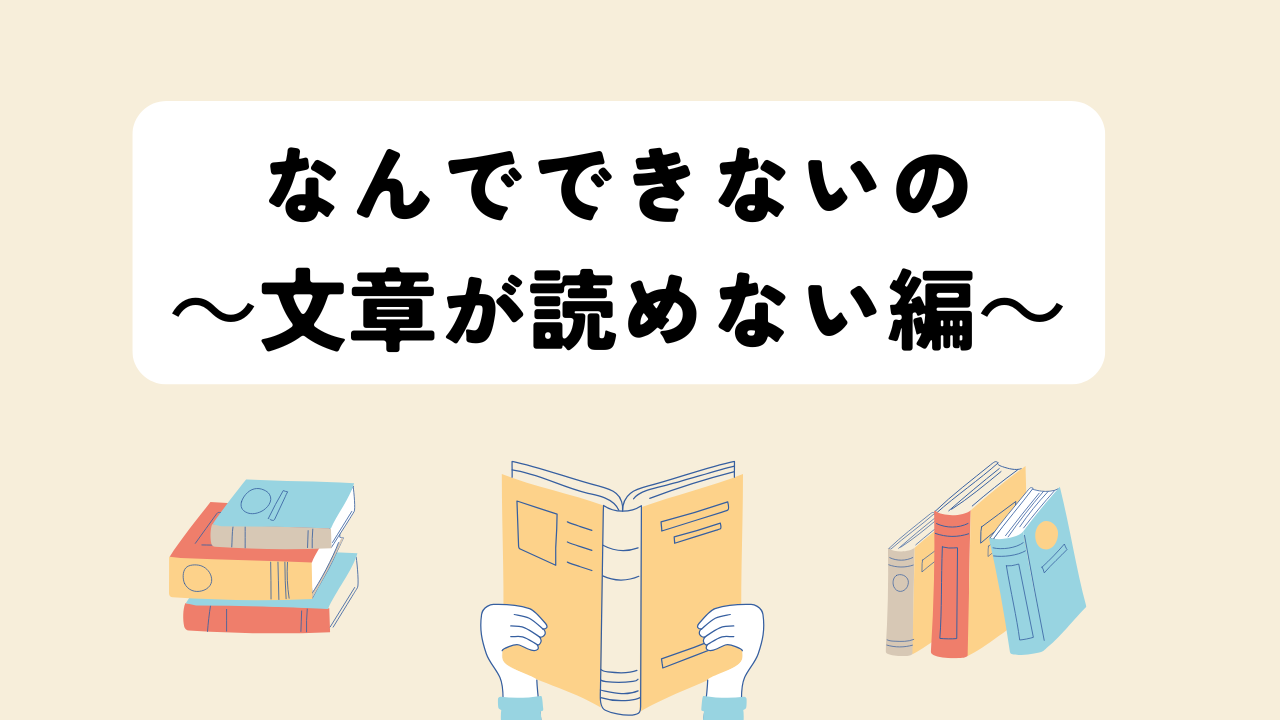


コメント