【本日のお悩み】
○同い年の子と比べると、うちの子は何か違う気がする
○周りの子よりも発達が遅い気がする
○どうしても同じクラスの子たちと比べてしまう
お悩み解消のための結論:気にしないで。自分の子どもだけを見て
保育園や幼稚園、小学校に入ると、同年代の子どもたちとたくさん接する機会が増えます。
すると、どうしても「あの子はもうできてるのに、うちの子はまだできてない」「周りの子と比べると、うちの子はまだ…」といった比較をしてしまいがちです。
比較してできないことばかりに目がいってしまうと、今度は「もしかしたら障がいがあるのかも」「いわゆるグレーゾーンと呼ばれる子なのかも」そういった不安が頭を独占し始めます。
そうなるともう、自分の子どもの一挙手一投足が怪しく見えてしまい、【普通の子】になってもらうために怒る回数が増えたり、必要以上に勉強させたりして、子どもを疲弊させてしまいます。疲弊した子どもを見た親は「もっと厳しくしなきゃ」と思ってさらに怒り、子どもはさらに疲弊して……最悪の悪循環ですね。
こうなる前に、視点を変えましょう。
平均値は目安。子どもの成長に違いがあるのは当然のこと
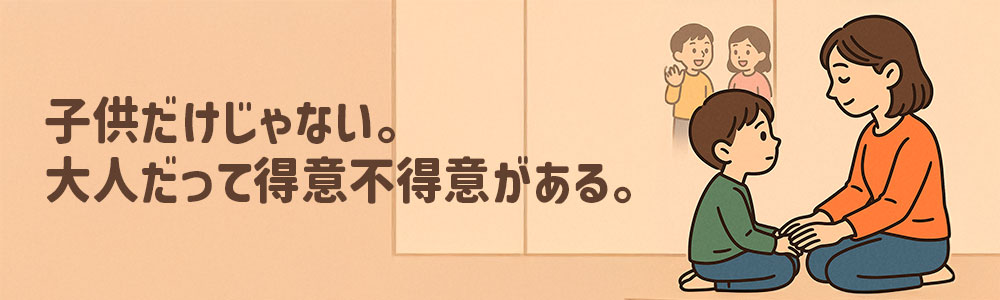
「とは言っても、他の子が目に入るとどうしても比べてしまうし、子どもから他の子の優秀な話を聞くと凹んじゃうんですよ」…それは確かにそうです。
でもよく考えてみてください。我々大人だって、個人によって得意不得意があるのは当然ですよね。
割り勘や買い物の会計前にサササッと暗算で金額を計算できる人もいれば、電卓を使っても間違えてしまう人もいる。
話を短くわかりやすくまとめてくれる人もいれば、話題があっちこっちに飛んで結局何が言いたかったのかわからない人もいる。
成長した大人ですら個性や能力が人によってさまざまなのに、まだ成長段階にいる子どもの発達がまちまちなのは、当然のことです。
「○歳頃から△△ができるようになる」といった平均値はありますが、あくまで平均値。
発達を折れ線グラフで表すと、きれいな一直線ではないそうです。でこぼこしてて行ったり来たり、人によってはその場でしばらくぐるぐる円を描いて急に伸びていくパターンもあるのだとか。
平均値はただの目安で、前後するのは当たり前という認識を持っておくといいですね。
子どもは想像以上に大人の態度に敏感
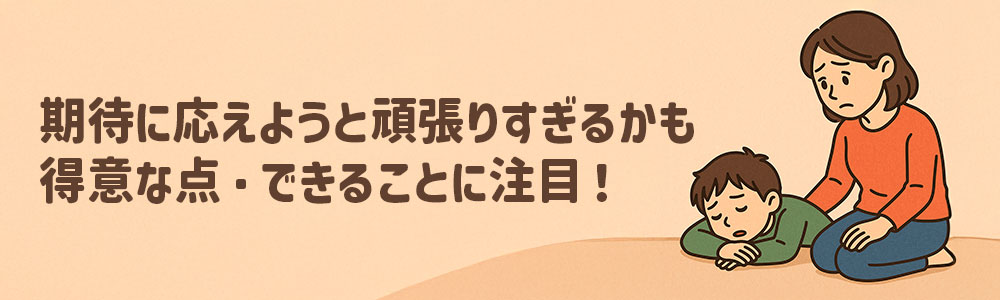
子どもは身近な大人の不安や心配を、肌で感じています。大人の心配を感じると、「もっとできるようにならなきゃ」と思って、がんばりすぎてしまうんです。
がんばりすぎるといつかは燃え尽きてしまい、できることもできなくなってしまうかもしれません。
子どものできないことに注目するのではなく、できることに注目するよう意識を向けてみてください。
できたことをたくさん褒めると、子どもは自信が持てるようになります。自信が持てたら、苦手なことにも自分から挑戦していくようになるかもしれませんね。
障がいかも?と思ったら専門機関に気軽に相談してみよう
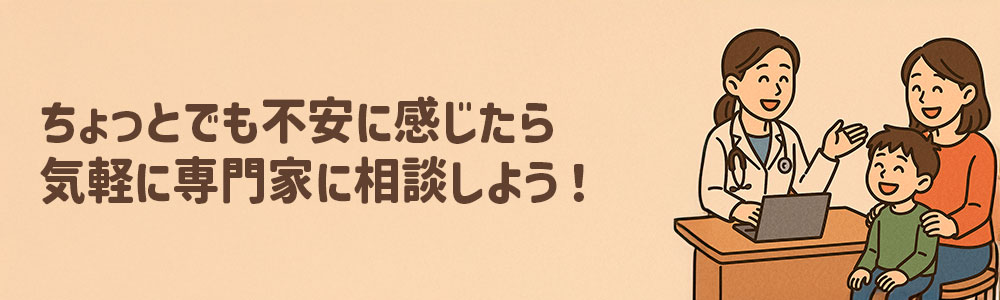
ちなみに障がいがあったとしても、早いうちから適切な支援と環境を作っていくことで、子どもは自分で対策を立てられるようになります。
「僕は音と人混みが苦手。今日は近所でお祭りがあるから、家から出ないようにしよう」
「私はすぐに忘れちゃうから、アプリでスケジュール管理しよう」
自分の苦手を把握し、その対策ができるというのは、生涯にわたって大切な力です。
障がいがあるからといって諦めるのではなく、その障がいと上手く付き合っていく方法を、大人は子どもに教えていかなければならないんです。
どうしても不安や心配が消えない方は、実際に福祉サービスや受給者証などの取得方法を調べておいてもいいかもしれません。具体的な対策方法を把握しておくことで、「この心配事はこうすれば解決できる」と思えるようになり、漠然とした不安感は解消されます。
さいごに
人と比べてしまうのは、我々大人でもあるあるです。
比較するのが悪いことではないですが、比較して欠点ばかりに目を向けてしまわないように気をつけましょう。
どうしても他の子どもと比べてしまう人は、自分の子どもができることに注目するよう意識してみてくださいね。
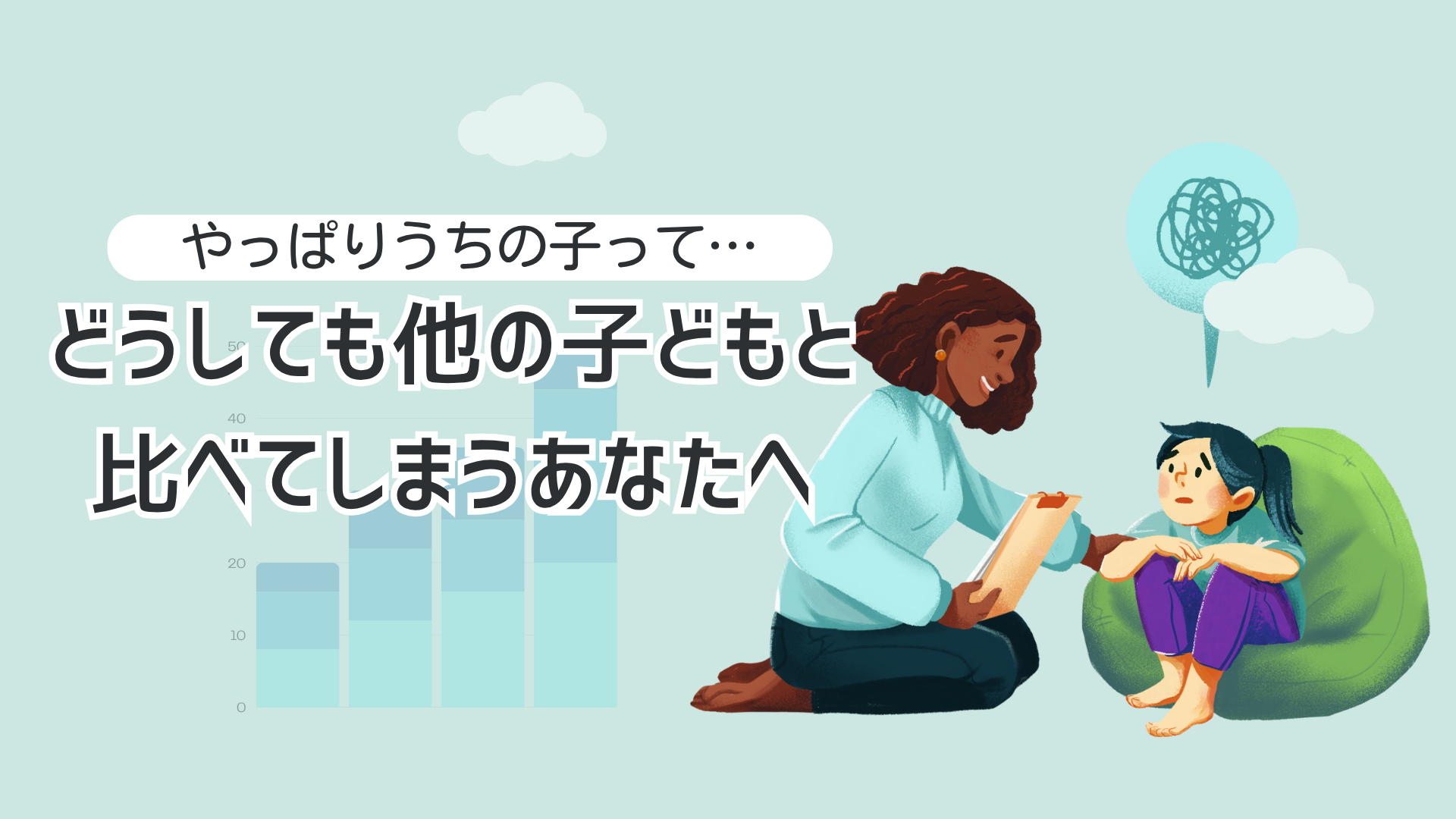

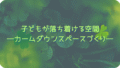
コメント