【本日のお悩み】
○療育や支援センターといった専門機関と、同じ支援を家庭でもしたい
○家庭ではどんな支援をすればいいか知りたい
○知識も技術もあるけど、自分の子どもだとなんか難しい
お子さんの成長を願うとき、「専門家と同じような療育を家庭でもしたい」と考える親御さんは少なくありません。しかし、結論からお伝えすると、それはとても難しいことです。なぜなら、家庭と支援現場では、お子さんとの「関係性」が根本的に違うからです。
この記事では、親子と支援者、それぞれの関係性だからこそできること、それぞれの良い点についてお話しします。
親子という特別な関係性だからこそできること
ご家庭での子育ては、支援センターや学校で行われる療育とは全く異なります。それは、あなたとお子さんが「親子」という、この世で一番近しい特別な関係にあるからです。
この関係性があるからこそ、以下の強みが生まれます。
- 深い愛情と信頼: 日常生活の中で無償の愛を注ぎ、積み重ねてきた信頼関係は、揺るぎない安心感をお子さんに与えます。この安心感があるからこそ、新しいことに挑戦したり、失敗しても立ち直ったりする力が育ちます。
- 家庭ならではの自然な学び: 食事や遊び、お風呂の時間など、ごく自然な生活の中で、お子さんの発達を促す機会はたくさんあります。支援現場では作り出せない、リアルな生活環境そのものが療育の場となります。
- 専門家が知らない情報: お子さんが「どんな時に笑うか」「何に興味を持っているか」「どんな時に不安になるか」といった、専門家も知り得ない些細な情報は、日々の暮らしを共にする親御さんだけが知っている貴重なデータです。
支援者という客観的な関係性だからこそできること
一方で、療育の専門家は、親御さんとは異なる「支援者と利用者」という関係性でお子さんと関わります。この関係性には、家庭では得られないメリットがあります。
- 専門的な知識と技術: 支援者は、お子さんの発達に関する専門知識を持っています。豊富な経験から、お子さんの特性に合わせた具体的なアプローチや、課題解決のための訓練を計画的に実行します。
- 客観的な視点: 感情が入らない客観的な視点から、お子さんの発達の現状や課題を冷静に分析します。これにより、親御さんだけでは気づきにくいお子さんの強みや、支援が必要なポイントを発見することができます。
- 家庭では難しい環境設定: 専門的な器具を使ったり、他の子どもとの集団活動を促したりと、家庭では再現が難しい環境を提供することができます。
大切なのは「家庭の良さ」と「現場の良さ」の連携
家庭での子育てと、支援現場での療育は、どちらが優れているということではありません。
家庭は、深い愛情と信頼をベースに、お子さんが安心して成長できる「心の土台」を育む場所です。 支援現場は、専門的な知識と客観的な視点から、お子さんの成長を力強く後押しする「もう一つのエンジン」です。
大切なのは、この二つの良い点をうまく連携させることです。
例えば、支援現場で学んだ専門的なアプローチを、ご家庭の状況に合わせて少しアレンジしてみる。 また、家庭での様子を支援者に伝えることで、よりお子さんに合った支援計画を立ててもらう。
このように、それぞれの強みを認め、補い合うことで、お子さんの成長を最大限にサポートすることができます。
お役立ちグッズ紹介
↓ABAという手法は、家庭でも取り組むことで、効果を発揮しやすくなります。子どもの気になる行動を変えるきっかけにもなると思います。(ABAについてはこちら→(応用編)子どもの『困った』行動は、ABAで解決できるかも)
↓子どもの自立を促しやすいとされるモンテッソーリ教育。この本は、今すぐにでも実践できる声かけにフォーカスしており、日常に役立つ内容です。
さいごに
「専門家と同じようにしなければ」と無理をする必要はありません。あなたは、あなたとお子さんの「親子」という関係性を活かした、素晴らしい子育てをされています。
ぜひ、家庭だからこそできる子育ての良さを大切にしながら、必要に応じて専門家の力を借りて、お子さんとの毎日を楽しんでください。
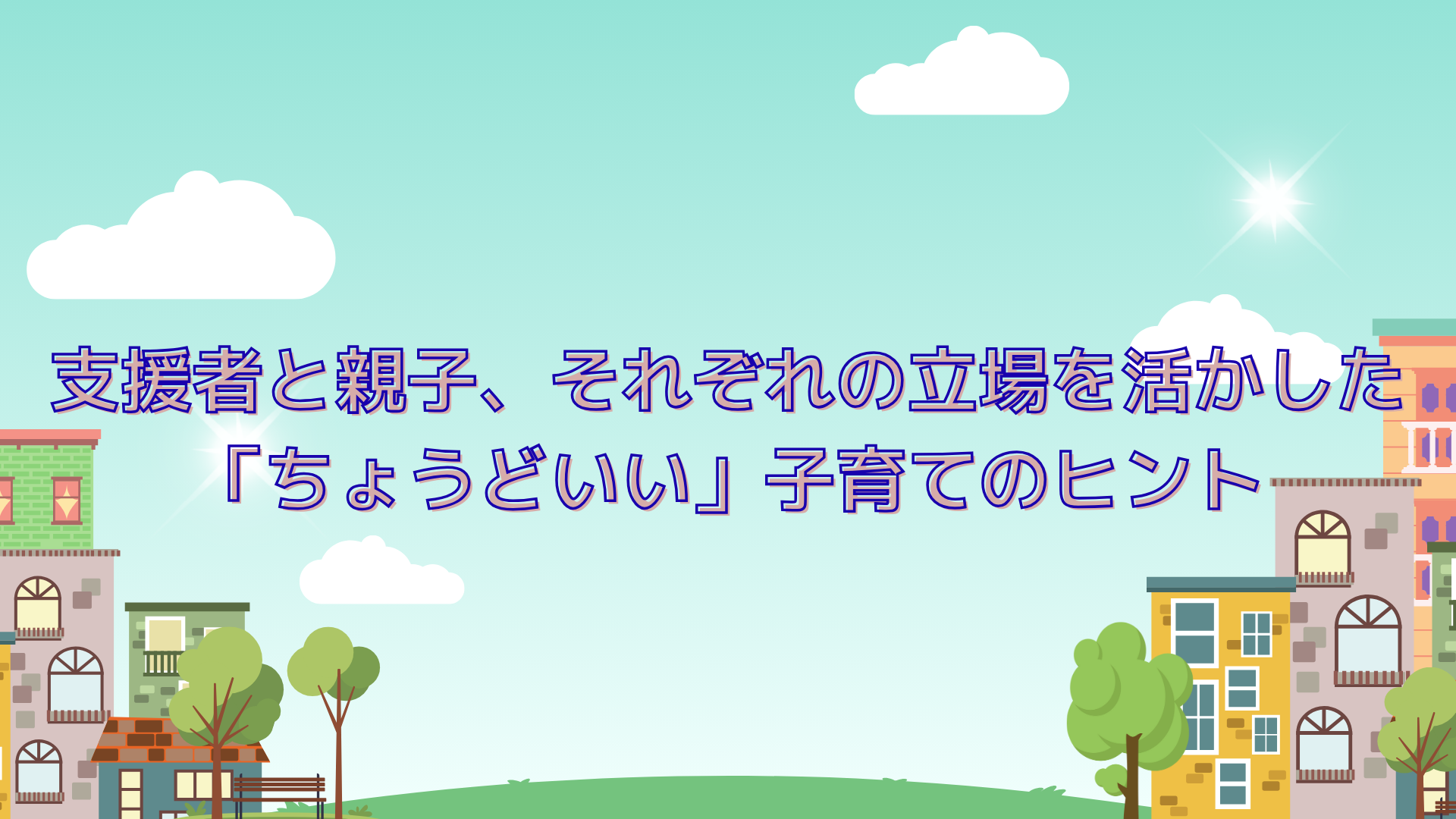

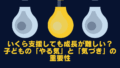
コメント