【本日のお悩み】
○子どもの言葉を増やしたい
○自分の気持ちをコントロールしてほしい
○人の気持ちがわかる子になってほしい
まだ上手におしゃべりできない、言葉が未熟な子ども。
イヤイヤしたり、急に泣き出したり、叩いたり…。
「何が言いたいの?」「どうしたの?」と、親も戸惑う場面って多いですよね。
そんなときに意識したいのが、子どもの感情を言葉にしてあげること。
これを「感情のラベリング」といいます。
感情のラベリングとは?
たとえば、子どもが突然泣き出したとき。
ただ「泣かないの!」と注意するのではなく、
「〇〇ちゃん、悔しかったんだね」
「それ、悲しかったね」
「うまくいかなくて、イライラしちゃったんだね」
と、子どもが感じている感情を代わりに言葉にしてあげること。
この“言葉のラベル貼り”が、子どもの心の成長にとって、とても大切なんです。
どうして大切なの?
子どもは、自分の気持ちをうまく言葉で表現できません。
だからこそ、大人が気持ちに「名前」をつけてあげることで、子どもは「これが怒りなんだ」「これが悲しさなんだ」と少しずつ理解していきます。
ラベリングを通じて子どもは、
- 自分の感情に気づく力(内省)
- 他人の気持ちを想像する力(共感)
- 言葉で伝える力(表現)
を育んでいきます。
昨今よく話題になっている、『「ヤバい」でしか感情を表現できない問題』も、子ども自身が言葉を知り、表現の幅を広げていくことで解決することができます。
子どもの語彙力を広げる一冊\ https://amzn.to/48uhT3k /
でも、何でも代弁すればいいわけじゃない
ラベリングは魔法のように思えるかもしれませんが、やりすぎはNG。
子どもの気持ちを“決めつけ”たり、“先回り”しすぎると、逆に自分の感情を見つめるチャンスを奪ってしまうことも。
子どもが「ううん、違う!」と否定するなら、その声に耳を傾けて。
ポイントは、
- 観察して、推測して、丁寧に言葉をかけること
- 「○○かな?」と疑問形で伝えるのも効果的
「〇〇ちゃん、悲しいのかな?」
「もしかして、怒ってる?」
こうすることで、子ども自身が自分の気持ちに向き合うサポートができます。
ラベリングの内容が、子どもの世界を広げる
大人がどんな言葉で感情を表すかによって、子どもの感情理解は大きく変わります。
たとえば、
- 「イヤ!」だけで済ませるのではなく、「がっかりしたんだね」「恥ずかしかったかな」など、より細かい言葉を使っていく
- ネガティブな感情だけでなく、「うれしいね」「ワクワクするね」など、ポジティブな気持ちもラベリング
こうした“感情の語彙”が増えていくことは、子どもの社会性や自己表現力の土台になります。
お役立ちグッズ紹介
↓見ているだけでも楽しめる、自分の気持ちを見つける絵本。
気持ちのジャンルごとに分け、さらに言葉の意味も詳しく解説。文字が読めない幼児~低学年の子どもまで、幅広く楽しめる内容です。
↓感情をキャラクターにして解説している、にぎやかな絵本。
上で紹介した絵本よりは読みごたえがあるため、小学生向きの内容です。その分、情報量はたっぷり。大人が読んでもためになる1冊です。
さいごに
子どもがまだうまく話せない時期こそ、大人の言葉が子どもの心の栄養になります。
- 泣いているときも
- 怒っているときも
- 喜んでいるときも
子どもの「心」にラベルを貼ってあげましょう。
感情を理解できる子は、他人とも上手に関われるようになります。
言葉が未熟でも、心はちゃんと育っているんです。
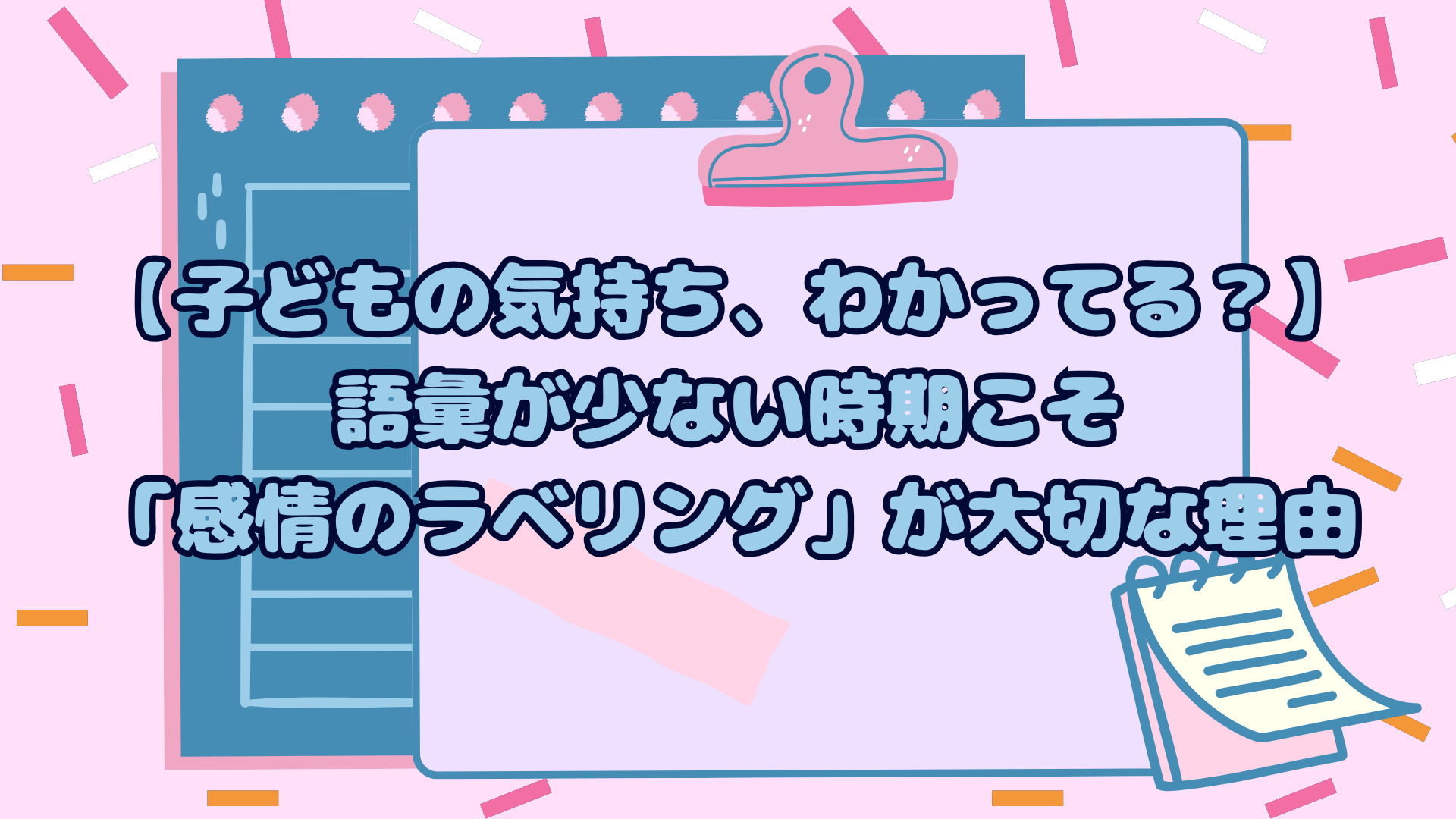
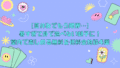
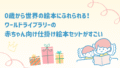
コメント