【エリクソンの発達課題とは】
人は、生まれてから年をとるまでのあいだに、「その時期ならではの心の成長テーマ」があります。
例えば──
・赤ちゃんのときは、「この世界は安心できる場所なのかな?」という感覚が育つかどうか。
・小さい子どもは、「自分でやってみたい!でも失敗しても大丈夫?」という気持ちと向き合う。
・思春期には、「私は何者?どんな大人になりたい?」と悩んだりする。
それぞれの時期に「心の試練」みたいなものがあって、それをうまく乗り越えると、自分らしく成長していけるという考え方です。
人生は長い冒険みたいなもので、ステージごとに「心のボスキャラ」が出てくる。そのボスを倒すと、ちょっとレベルアップして、次のステージを生きる力が手に入る──そんなイメージです。
この「年齢ごとに向き合う心のテーマ」のことを、心理学者のエリク・エリクソンは【発達課題】と呼びました。
学童期の発達課題は「勤勉性 vs 劣等感」
小学校に入学すると、子どもたちは社会の中で「評価される」機会が一気に増えます。
テストの点、運動の速さ、発表の上手さ、友達との関係…そんな中で子どもたちは、「自分は何が得意で、何ができるか」を探りながら育っていきます。
6〜12歳頃の子どもは、努力して何かを“やり遂げる”経験を通して、「自分にもできる」=勤勉性を育てていく必要があるんです。
たとえば
・九九を覚えた
・逆上がりができた
・宿題を自分で終わらせた
・友達と協力して何かを成し遂げた
こうした体験が、「努力すればできる」「自分は役に立つ」という自己効力感や自信につながります。
反対に、
・何をやっても失敗ばかり
・いつも他の子と比べられる
・失敗を責められる
といった状況が続くと、「どうせ自分には無理」と感じるようになり、劣等感が育ってしまいます。
親・保護者ができること
この時期に大切なのは、“結果”より“努力”や“継続”に目を向けること。
たとえば
✅「100点」より「毎日ちょっとずつ頑張ってたね」
✅「勝った」より「最後まであきらめなかったね」
また、勉強だけにとらわれず、「絵が上手」「優しい」「整理整頓が得意」など、子どもの強みに目を向けることも大切です。
劣等感が強くなると、
・チャレンジを避ける
・他人との比較ばかり気にする
・「どうせダメだし…」が口ぐせに
・やる前から諦める傾向
家庭が“競争の場”になると、子どもは安心できる居場所を失ってしまいます。
だからこそ、家では「比べない」「認める」「安心できる」ことが必要です。
お役立ちグッズ紹介
↓家族で受講できるオンライン英会話
幼児~大人まで、学齢に合わせたレッスンが豊富です。今や小学校でも英語が必修科目に……苦手意識が芽生える前に、「英語は楽しい!」と感じてもらいたいですね。
↓周りとの比較が始まる時期だからこそ、子どもには自身の成長をモチベーションにしてほしいもの。
学校で学ぶのはちょっと難しい、発想力や論理的思考の育成に期待できる教材です。
話題のSTEAM・プログラミング教育教材なら【ワンダーボックス】
さいごに
学童期は、「できた!」の体験を積み重ねていく時期。
小さな達成感の積み重ねが、大きな自信につながります。
大人は“応援団”。「やってみよう」「よくがんばったね」と、その子自身の努力や姿勢を見つめて声をかけることで、勤勉性はしっかりと育っていきます。
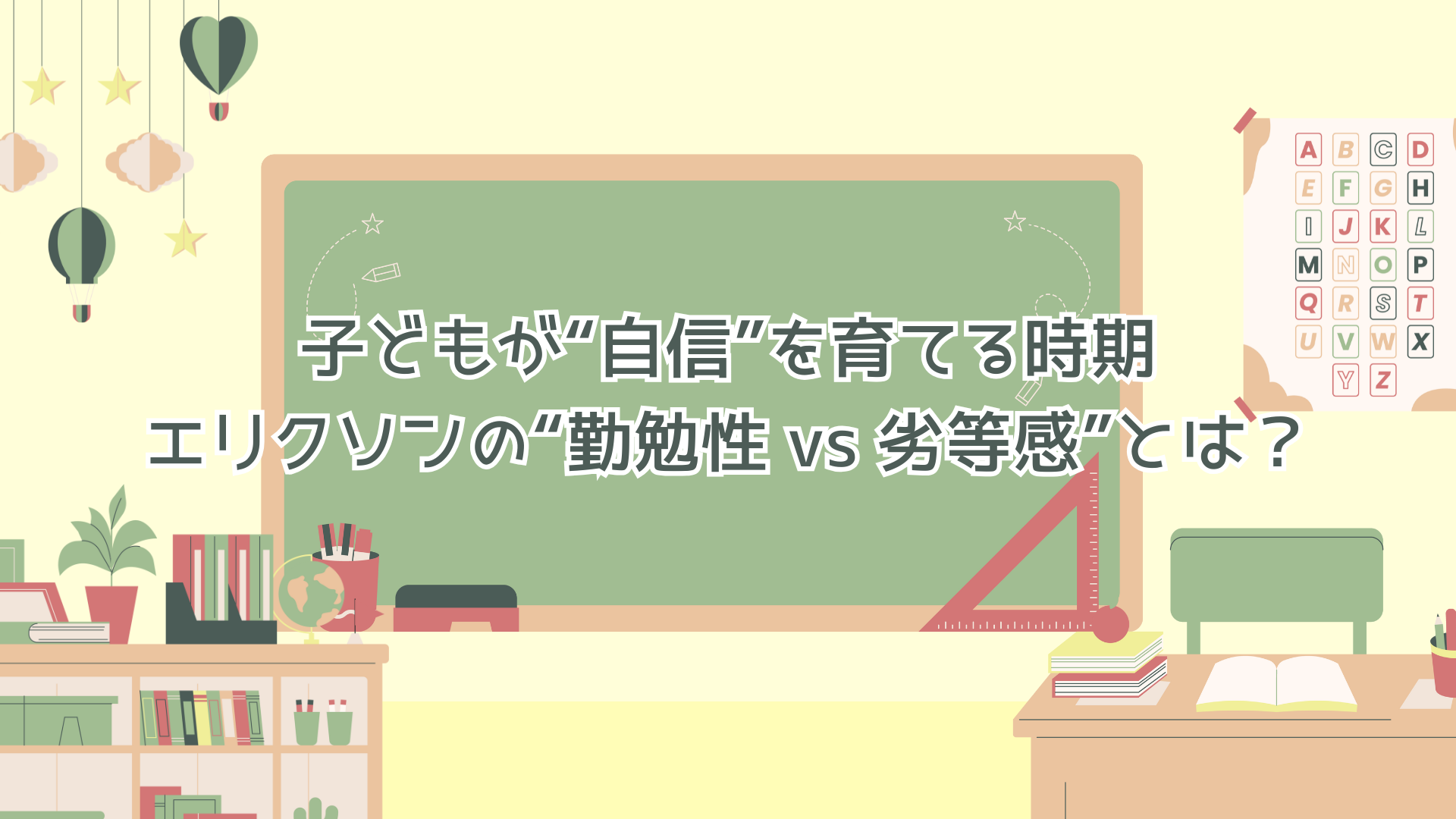
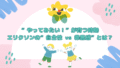
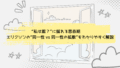
コメント