【本日のお悩み】
○去年までは宿題や勉強もがんばってたのに、学年が上がってサボりがちになった
○子どもが急に反抗的になった
○小学4年生になって、子どもが変わった気がする
お悩み解消ヒント:それ、【小4の壁】かも
小4の壁は【9歳の壁】【10歳の壁】とも呼ばれています。心理学では【ギャングエイジ】という、なかなかに物騒な名前がつけられている時期です。
なぜこの年代になると、反抗的になったり勉強をサボるようになってくるのでしょうか。
以下、各分野にスポットを当てて解説します。
算数
これまでの算数は、整数の足し算や引き算、九九の暗記など、具体的に想像できる問題がほとんどでした。
でも小学4年生の算数は、小数点や分数といった、抽象的な思考が必要になってくる問題が増えてきます。文章問題も難解になり、「文章問題に数字が2個あるから、適当に足しておけばいいや」という手法が通用しなくなります。
国語
目にする文章が長くなり、漢字も画数が多く複雑なものになっていきます。
さらに、名詞や動詞、形容詞といった文法(品詞の分類)も、小学4年生から習い始めます。文法の本格的な勉強は中学校に上がってからですが、言葉のルールを理解するというのは、なかなかに大変です。
しかも品詞の理解は、中学で勉強する古文や英語の基礎にもなるため、今後の学習にも影響してくるというのが難しいところです。
こういったことから、勉強をサボっているように見えるのは、もしかしたら内容が理解できないために「勉強したくてもできない」状況にあるのかもしれません。
友人関係
「一緒に遊べば友達」という関係から、「価値観や興味が合う子」との結びつきが重視されるようになっていきます。特に仲のいい子ができたり、グループもできてくる時期です。
特に女子はグループ化が激しく「グループに入れてもらえない」「仲間外れにされる」など、言語による人間関係の駆け引きが生じてきます。
男子も「俺の方ができる」「あいつは下手」といった序列づけが始まりやすく、ケンカが暴力ではなく、言葉や態度での争いになってきます。
他者との比較
「自分はこう思う」「あの子は違う」といった、自分と他人は違うという認識が強まってきます。
これは子どもの自我が本格的に発達している証です。
そのため他者と自分を比較することが増え、比較してマウントをとったり落ち込んだりということが見られてきます。
学校は「テストの点数」「足が速い」といった、目で見てわかりやすい結果が出やすいため、比較も起こりやすい環境です。
思春期の入口
一般的に、思春期は10歳頃から始まると言われています。思春期は心身ともに大きな変化があるため、不安定になりやすい時期でもあります。
体の変化:身長の急な伸び。女子は乳房が、男子は精巣が発達を始める。性的なことへの興味・関心が深まる
心の変化:親よりも友人関係を重視するようになる。そのため親に反抗的になったり、会話が減る
発達ユニークって、面白い視点かも\ https://amzn.to/4psUaXc /
具体的な方法:壁を“乗り越える”というより“付き合う”意識
小4の壁を前にして、誰よりも戸惑って困っているのは子ども本人です。子どもなりに失敗を重ねながら模索して、道を探り始めたところです。
自分で立ち上がって進もうとしている子どもに対して、大人ができることは「観察とサポート」。決して「干渉・お節介なアドバイス」ではありません。
トラブル内容によっては大人の介入が必要な場合もありますが、基本のスタイルは見守り。子どもを見守り、自立の芽を育てることが、将来の中学・高校でも効いてきます。
大人ができる行動はシンプルに3つ。
①話を聞く姿勢を持ち続ける
友人関係を重視するようになり、大人に話をしなくなった子どもが話しかけてきたときは、もしかしたら何らかのヘルプサインかもしれません。
だからといって「これはこうするべき」「それは絶対あり得ない」など、強制したり否定する言葉は使わないようにしてください。何度も言いますが、大人の基本スタイルは見守りです。
もし、どうしても助言したいときは「これはこういう方法もある」「私だったらこうするけど、あなたはあなたのやり方があるかもしれないから、考えてみて」というように、子どもが選択できるような言い方を心がけてみてください。
②感情を否定せず受け止める
子どもから反抗的な態度・言葉を向けられると、悲しいと同時に怒りたくなる気持ちもわいてきます。
大人の皆さん、思い出してみてください。思春期って、何に対してもずっとイライラしていませんでしたか?(私はしていました。親に長文のメールや手紙を書いていました。「その態度は親としてどうなんですか?」等と、今思えば申し訳なさでいっぱいです…)
とはいえ、イライラを向けられるとこちらもイライラしてくるもの。人間だもの。
難しいですが、コツは「一拍おいてから返す」。
「なんでそんな言い方するの?」「そんな言い方やめなさい!」ではなく「疲れてるんだね」「イライラしてるみたいだね」と、感情を指摘するのではなく、ラベリングしてあげることで、子どもは自分の気持ちを客観視しやすくなります。
(思春期の対応については、後日また記事にして詳しく解説したいと思います)
③子どもが選ぶ場面を日常的に増やす
子どもの自立という観点からも、今までは大人が決めていたこと(服の購入や習い事の選定、外出先など)を子ども自身に選んでもらう場面を増やしていきましょう。
小さなことでも構いません。自分で選択・決定できたという自信は、自我の芽を育てることにつながっていく、重要な要素です。
(思春期の対応についてはこちらも参照してみてください。)
お役立ちグッズ紹介
↓児童精神科医が、自身の子育て経験からも学び「子育てが不安な親」に伝えたいことを綴った一冊。
読みやすく、内容も充実しているので、一度読んでみることをおすすめします。
さいごに
大切なことは、「大人はいつでもあなたの味方である」ということを、言葉としても態度としても、日常的に伝えていくこと。
身近な大人は子どもの避難場所として常に機能できるように、意識しておきたいですね。

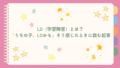
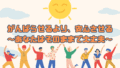
コメント