ジャン・ピアジェ(Jean Piaget)は、スイスの心理学者であり、生涯を通じて「子どもはどうやって考えるようになるのか?」という問いを追求しました。
彼は子どもに質問を投げかけたり、観察したりすることで、子どもの思考が大人とは根本的に異なると気づきました。
ピアジェが考えた4つの発達段階について、それぞれ紹介・解説していきます。
「もし戦争がなくなったら、世界は平和になるのかな?」
「お金より大事なものって、なんだろう」
「私って、何のために生きてるの?」
そんな一言にドキッとしたこと、ありませんか?
12歳ごろからの子どもは、ピアジェの発達理論でいう形式的操作期に入ります。
今回は、この時期に育つ「抽象的な思考」や「自己理解」の特徴と、親の関わり方をお伝えします。
形式的操作期とは?
この時期の子どもは、目に見えることだけでなく、「もしも」「なぜ」などの抽象的なことを考えられるようになる段階に入ります。
ピアジェはこれを、形式的(形式上の)思考が可能になる時期と定義しました。
つまり、今までは“具体的なもの”を前提に考えていたのが、
この時期から“現実にないこと”や“仮説”を立てて、論理的に考えられるようになるんです。
この時期の特徴は以下の3つ。
❶ 抽象的思考が発達する
「正義とは?」「平等とは?」「自由とは何か?」など、
目に見えない価値や概念について考える力が育ちます。
🔸例:
・ニュースに対して自分の意見を持つ
・哲学っぽい問いを投げてくる
・「でもそれって本当に正しいの?」と疑問をもつ
❷ 仮説的思考・問題解決力が伸びる
「もしこうしたら、こうなるかも」と仮説を立て、検証したり比較したりできるようになります。
🔸例:
・テスト勉強のやり方を自分で工夫する
・友達関係のトラブルを“冷静に分析”できる
・将来の進路や職業について自分で調べ始める
❸ 自己理解と自意識が高まる(=思春期まっさかり)
この時期は、自分を客観視したり、「他人からどう見えているか」を強く意識しはじめます。
そのため、
・急に反抗的になる
・親に「放っておいて」と言いながら、気にしてほしい
・将来の自分像や、アイデンティティに悩む
といった“思春期あるある”が頻出します。
でもこれも、「自己という存在」について真剣に考え始めている証拠なんです。
中高生向け。セルフコントロールを身につける\ https://amzn.to/44mOrtJ /
親にできる関わり方
☑「正解よりも、考え方を認める」
この時期の子どもは、大人と同じくらいの抽象的思考ができるようになります。
だからこそ、「親の言うこと=正しい」という関係性ではなく、“一人の考える人間”として尊重する姿勢が大切です。
🔹NG:「親の言うとおりにしなさい」
🔹OK:「あなたはどう考える?」「それも一つの見方だね」
☑ 対話の“土俵”に乗る
「面倒な質問」も、実は対話のチャンス。
「生きる意味ってあるの?」と言われて戸惑っても、「あなたはどう思ってるの?」と返してみましょう。
一緒に考える姿勢が、信頼関係につながります。
☑ 自己探求のサポートをする
🔷自分の好きなこと・得意なことを整理するワーク
🔷将来の夢や関心について話す時間
🔷好きな本・映画・ニュースを語り合う
こうした活動を通して、子どもは「自分ってなんだろう?」という問いを育てていきます。
自分のやりたいことって何だろう……\ https://amzn.to/47XMx59 /
お役立ちグッズ紹介
↓大人でも楽しめる哲学の入門書。
「なぜ人殺しはいけないのか」――この疑問に、あなたは何と答えますか?
有名な哲学者や歴史の流れを踏まえつつ、いわゆる『厨二病』と呼ばれる年代が抱きやすい哲学的課題を深堀していきます
さいごに
「問い」は、思春期から生まれる。
形式的操作期に入った子どもは、これまでとは比べものにならないほど“深く”“広く”考える力を持ち始めます。
親からすれば「何を考えてるかわからない」「いきなり反抗的になった」と感じることもあるかもしれません。
でも、それはまさに「考える力」が成熟し始めている証。
子どもはもう、“親の背中を見て学ぶ存在”から、“自分の目で社会を見ようとする存在”へと変わっていくのです。
この時期こそ、親が「一歩引いた対話相手」になることが、子どもにとっては大きな支えになるかもしれません。
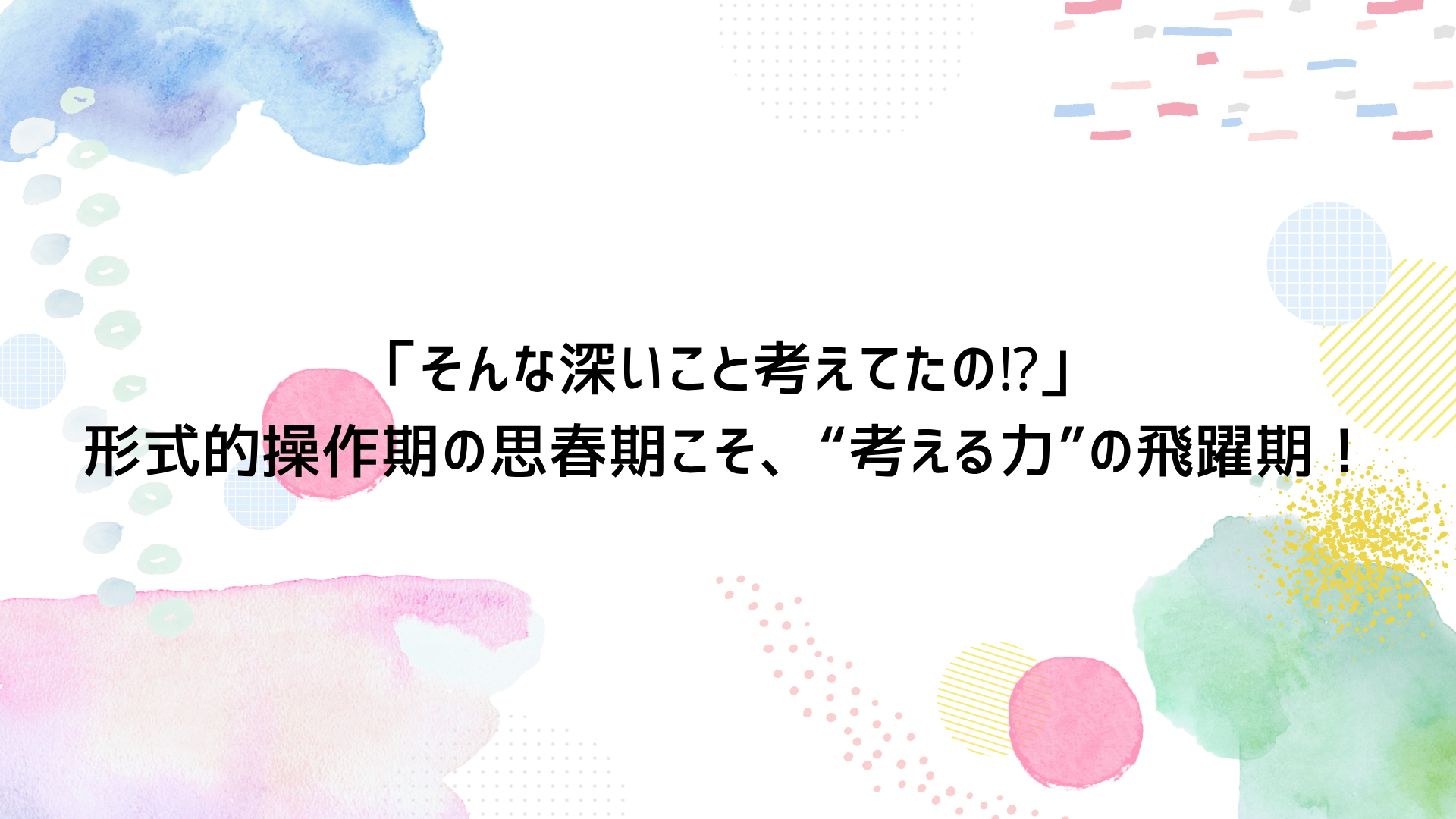
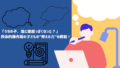
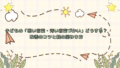
コメント